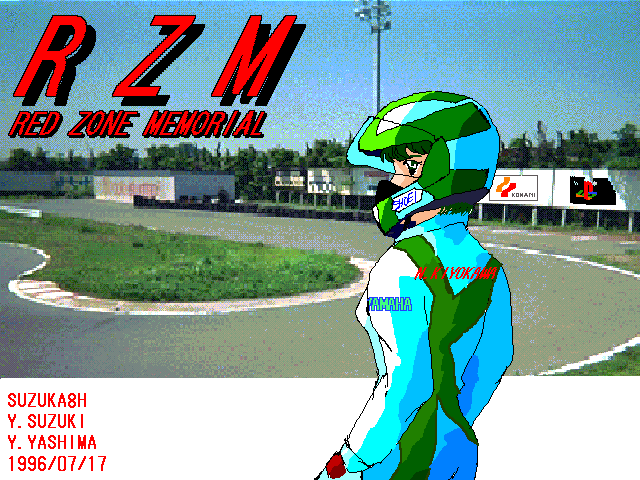BGM ORIGINAL SOUNDTRACK ALBUM PATLABOR VOL.5
#2 「ヘヴィ・アーマー」
制作

「俺、走るよ。清川さんのために走るよ」
「・・・公くん」
企画 原作 執筆 鈴木 良和
「プラグかピストンか?・・・ま、おれはピストンと見るがね」
「先生?」
キャラクターデザイン 矢島康之
「詩織ちゃん、私、怖い、怖いよ」
「駄目よ、メグ。ちゃんと見るのよ。最後まで」
シリーズ構成
設定監修 浅野光耳
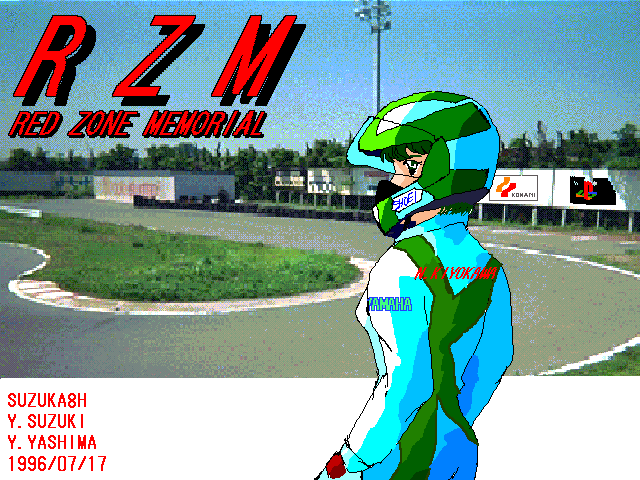
第一回 「夜明けのTZR」
きらめき市郊外 某峠 四月 早朝
夜明け前、茜色に染まりはじめた東の空を背景にして、山の稜線が深い藍色を縁取り
浮かび上がる。
ひんやりと冷たい空気を切り裂くように、2つの排気音が山あいにこだまする。
ライトをもつれ合うように交差させつつ、2台のオートバイがアスファルトを駆け抜
けていく。(てへっ、詩的に始めちゃった)
「頂上にいたTZRか?」
素早く左右に体重移動をさせながら、前を走るバイクのライダー(男)が、誰に言う
のでもなくつぶやいた。
「下りで追われまくるなんて、ショックでかいぜ」
彼の乗るCB400(HONDA CB400スーパーフォア)を、TZR(YAMAHA TZR
250)が攻めたてていた。
そのTZRは、頂上付近のパーキングエリアで見かけたものだった。
何事かマシンの様子を見ていたようだったが、CBで流し加減で峠を下っているうち
に、追いついて来たのだ。
前を走るCBのライダーが、フルフェイスのヘルメット中で苦々しい口調で言った。
「いやー、俺もまだまだ若いねえ。この峠も、まだ、あまり走り込んでないから、本気
出したらいけないよな」
(嘘つけ、結構、本気だったくせに)
実際、彼のCBは、かなりのハイスピードで各コーナーを攻めていた。
そのCBを、ほんの少し上回るペースで、TZRは攻めていた。
ラインが交錯するため、前に出られはしないが、それでもその速さは彼も認めざるを
得ない。
絡み合うラインが、2本の白い線を薄明かりの中に浮かび上がらせる。
タコメーターの針が激しくダンスを繰り返し、カスタムメイドの集合管が、エキゾー
ストと言う名のホルンを山あいにこだまさせる。
急制動を繰り返し強いられ、ブレーキディスクが熱を帯びる。
それでもなお、TZRのライトはバックミラーに、今にも張りつかんばかりに接近し
ていた。
(抜けるもんなら抜いてみろ!
最速ラインを取ってるのはこっちなんだ。そうそう抜けるものか!)
実際それは正しい。ブロックしているのではなく、最速のラインを取っていれば、わ
ずかな速度差では抜くことは難しいものだ。
だが、この時、後方のTZRのライダーの口元が、フルフェイスのヘルメットの中で
ニヤリと笑いを浮かべた。
そして、決着は不意にやって来た。
左コーナーの進入口、CBはぎりぎりまでブレーキを我慢した。いや、少なくとも、
CBのライダーの彼はそう思った。
だが、TZRはそのインからCBを刺した。
「ばか!!オーバースピードだ!!」
『コケる』
彼はそう思った。
TZRは、ブレーキの明かりをテールに光らせながら、その車体を傾ける。
そして、その左ステップが、アスファルトに触れ火花を散らす。
「そら!・・・」『見たことか』
一瞬、彼はそう思った。だが、その直後だった。
「何イ!!」
彼は信じられない思いをする。
ゆらゆらと揺れたTZRのテールランプが、かげろうのように揺らめきながら、立ち
上がり、コーナーを駆け抜けて行ったのである。
「おいおい!・・・驚いたね、こりゃ」
駆け降りていくTZRの光を見送って、彼はCBを路肩に止める。
『後方排気のチャンバーだったからRR(ダブルアール、TZR250Rの事)じゃな
い。
軽量化と、ブレーキ強化の下り用チューニングか・・・。
それにしても無茶しやがる』
そう思いながら、今、抜けてきたコーナーを振り返り見る。
そして、声を出して笑いながら言った。
「いやー、負け負け。完全に俺の負け。
速い奴ってのはどこにでもいるもんだなあ」
そう言った後、彼はCBのタンクと同じ黄色をベース色としたヘルメットをとる。
年齢は20台後半か? 日焼けした肌に太い眉、短く刈り上げた髪、太い首は、いか
にも運動で鍛え上げられた、といった印象を受ける。
そんな彼の口からこぼれたのは、こんな台詞だった。
「あの腰のライン、あれは女だな」
(・・・どこを見てたんだ? どこを?)
そして、その黒い瞳で、眼下に広がる街並みを見ながら、ため息と共につぶやいた。
「きらめき市か。就任早々、楽しみな事だぜ」
ため息とは裏腹に、その表情はいかにも楽しそうだった。
(ステップをこするのは、大変危険ですので、絶対にまねしないでくださいね)
その10分ほど後、そのTZRは、鉄筋コンクリート3階建ての、かなり大きな一軒
のバイクショップの前で、その2サイクルエンジンの鼓動を止めた。
「お帰りなさい。お嬢さん」
そのTZRを、作業用のつなぎを着て掃除をしていた若い男が、出迎える。
ヘルメットをとりながら、TZRのライダーが答える。
その姿は、緑色の髪をボーイッシュに短く切り、一見すると男の子にも見られそうな
少女だった。
「もう、お嬢さんてのはやめてよね。どう見ても柄じゃないでしょ?
望でいいよ」
男は、ためらいつつも言われた通りに答える。
「・・・お帰りなさい。望さん」
「ハイ、ただいま」
その望という少女は、TZRをひいてガレージに入れる。
「お帰りなさい。望お嬢さん」
ややからかうような口調で、そう言ったのは、頭に白い物が混じっている年配の男
だった。
その声に、望は苦笑いを浮かべながら答える。
「もう、栗田さんまで」
その、栗田と呼ばれた男は、望からTZRを受け取ると、スタンドにその後輪を掛
けながら言った。
「それでどうです。仕上がり具合は?」
「うん、悪くないけど、金原さんが使うとなると、もうちょっと低速を生かした方がい
いんじゃないかな?」
栗田はエンジンから、プラグを取り出し、焼け具合をみる。
「いい色に焼けてます。有効な回転域を使ってくれましたね」
「うん。まあね」
望は照れたような笑いを浮かべてそれに答えたが、ステップを見ていた栗田は、それ
に釘を刺すような言い方をする。
「でも、攻めましたね?」
「え?いや、その・・・そ、そりゃ、ちょっとばかりは攻めたけど、全然本気じゃなかっ
たよ。
お客さんのTZだし」
栗田は弱ったように首を振る。
「いけませんねえ。望さんほどの腕になると、公道で全開に攻めても、得る物は何もあ
りませんよ。
それに、事故でも起こしたりしたら、今まで頑張って両立してきた水泳も、無駄にな
ってしまいますよ・・・」
「・・・はい、ごめんなさい。これから気をつけます」
望は頭をぺこりと下げて謝った。
それを見て、栗田はうなずきながら続ける。
「私は望さんのお父さまから、留守を預かる身です。
望さんに万が一のことがあれば、申し訳もありません。以後注意してください。
そもそも、・・・」
栗田の話が続くと判った望は、内心、
『あーーあ。またか』
と思った。
「望さん。学校に遅れますよ」
という声を、渡りに舟と、そこからすたすたと逃げ出したのだった。
(ま、良くあるパターンだね)
そのバイクショップは、彼女自身の家でもあった。
望は自室で制服に着替え、登校しようと店舗の裏口から外に出た。裏口とは言っても
住居としての玄関にあたり、そこには”清川”と書かれた表札が掛けられていた。
玄関を出た正面には、先程まで、彼女が攻めていた山並みが連なっていた。
「あのCB、速かったな」
その山並みを見ながら彼女はそう言って、通い慣れた学校への道を歩き出して行っ
た。
彼女の名前は清川望。
私立きらめき高校の3年生に、この春なったばかりである。
その名前は、私立きらめき高校では、つとに有名だ。それどころか、”超高校級スイ
マー”として、全国からも注目を集めるほどの選手だったのだ。
だが、彼女にこのような私生活がある事は、ごく一部の者しか知らないことだった。
そして、この日の夜明け前に、峠でおきた出来事が、彼女の生活、また彼女に関係す
る者達に、様々な影響を与える事になるとは、この時、彼女が知る由もなかった。
to be continue RZM「2」
SS RZM(2)228-Line
第2回 「CBの男」
「おはよう、清川さん」
きらめき高校の正門前、望はある男子生徒に、朝の挨拶をされた。
「あ! お、おはよう公くん」
望の頬が赤く染まる。
彼女に声をかけた男子生徒、名前を主人 公(ぬしびと こう)と言う。
ある意味、きらめき高校の中で、彼は望に勝るとも劣らぬ有名人だ。
入学した当時は、目立たない、ごくごく平凡な生徒だったのだが、この2年間の彼の
成長は著しく、成績は学年トップ、スポーツは万能、容姿端麗で性格もいいと言う、何
拍子も揃った優秀な生徒となっていたのである。
当然、女子の間でも人気は高く、彼に秘かに想いを寄せている者は多い。
だが、この公という少年の最大の欠点は、そう言った異性の心情には、とんと無頓着
ということだった。
(それが救いといえば、救いという考え方も、あるにはあるか?)
ともかく、公にあこがれ、想いを寄せている多くの女子の中に、望も入っていたので
ある。
望と公が初めて出会ったのは、実のところ、結構早い時期だった。
それは1年の2学期が始まってすぐの事で、望は体力造りのために、早朝のロードワ
ークをこなしていた。 その時に、公と出会ったのである
当時はそれほど親しいというわけではなかったのだが、ある事件をきっかけにして、
二人は一つの秘密を共有する事になる。
それは、2年の夏、公が望の家(正確に言うなら、そこのバイクショップに)、公が
オートバイのカタログをもらいに行った時の事だった。
「あれ、公くん。どうしてここに?」
「え?ええと、カタログをもらいに」
正直に、事の次第を説明する公に、苦笑いをしながら望が言った。
「公くん、オートバイの免許持ってたかしら?」
「も、持ってるには持ってるけど。・・・き、清川さんこそ、その格好・・・」
望を指さし、そのまま固まる公だった。
なにしろ、望は彼女のためにしつらえたのではないか?と思えるほど、彼女によく似
合ったレーシングスーツを着こなしていたのだ。
それは、免許を持っていない方が不自然というものだった。
きらめき高校では、自動2輪免許(すなわちオートバイ免許)の保持そのものは、届
け出た上で許可されている。
だが、オートバイの所持は禁止されている。つまり、法律で許されている物について
は許可をする。だが、バイクを持つことは、まだ時期尚早。と言う考えのようである。
賛否両論あろうが、そう言う校則になっていた。
しかし、現実に免許を持っていれば、乗りたくなるのが人情というものだろう。影で
こっそりという者は後を絶たなかった
公も、望も、お互いの立場が手にとるように判った。だが、望にはこれ以上ない強み
があった。
と言うのは、望がバイクに乗るには、『家の手伝い』と言う大義名分があった。
実は、望の父は、全国に名が知られたオートバイのエンジンチューナーで、望の家自
体が、レーシングチームを持つ程の大型バイクショップ、兼、オートバイのチューナー
なのだ。
望はそこでテストライダーという役目をおっていた。
チューニングされたマシンの最終チェックをすると言う、大事な役目である。
望はそれにより、堂々とバイクに乗ることが出来た。
ただし、他の生徒への影響を考え、それを公にすることは出来なかったが。
望はそうだったとしても、公の方はどうだろうか? 実際のところ、公もバイクには
乗りたいし、自分のバイクを欲しいと思ったことも1度や2度ではない。
だが、現状では、バイクのカタログを手に入れ、バイトなどで資金を集め、来るべき
時に向けて、想像を巡らすのみだった。
(判るなあ。その気持ち・・・)
「いやあ、実はさ・・・」
望は自分の事を正直に公に言った。別にやましい事などなく、公が公言しなければ、
何の問題もないことなのだから。
望は、公のそう言った面は信用していた。
公と望の付き合いが変わったのは、それからだった。
公は望の家、すなわち、バイクショップに顔を出すようになり、ついには、そのレー
シングチームに入り、スタッフとして、クローズドレース(チーム内での内輪のレース
の事)の手伝いまでするようになっていた。
そして、2年生の終わり、春休みにはサーキットライセンスまで取ってしまったの
だ。
(サーキットライセンスに関する校則はない・・・)
「そういえば、清川さん、橋本先生、産休なんだって?」
「うん、そうなんだ。仕方がないことだけど、やっぱり困るな」
校門から玄関までの短い距離を、望と公は並んで歩いていた。
二人の間に名前が上った、橋本というのは水泳部の顧問で、出産を控え休暇に入って
いた。その事を話していたのだった。
「臨時の教師が来るって話でしょ?」
「そりゃ、来るけど、練習の予定、狂っちゃうだろうなあ」
「うーーん、そうだろうね」
そうこうしている内に、二人は校舎に入った。
「それじゃあ、また、ショップの方に顔出すから」
「うん、みんな、待ってるわよ」
「・・・みんな?」
ほんの少しばかり寂しそうな表情でそう言った公に、望は聞き返す。
「え?」
「いや、なんでもないよ。・・・じゃあね」
「うん」
二人はそう言って、別の下駄箱へと別れていった。
ちょうど、その頃、きらめき高校の駐車場に一台のバイクが入って来た。黄色いタン
クのCBだった。
それを目撃した者は、奇妙な違和感を覚えた。それは、乗っていた者がスーツ姿だっ
た事に影響されたのだろう。
そして、そのライダーが、タンクと同じ色のフルフェイスのヘルメットをとる。
それは、その日の朝、郊外の峠で、望と一勝負(笑)した男だった。
男は、右のバックミラーで髪を整え、ネクタイを締め直す。
男は校舎を見上げると、右手の人指し指と中指をそろえ、自分の額に軽く当ててか
ら、前方に少し離してからこう言った。
「まあ、短い間だけど、よろしく頼むわ」
「こちらは京間 郡司さんです。産休をとられた橋本先生の補助教員として、これから
鞭を振るっていただきます」
CBのライダーは、職員室で、居並ぶ教師たちの前に立っていた。
朝礼で教頭に各先生に紹介されていたのだ。
「京間先生には、社会科を受け持っていただきます。それと、水泳部の顧問代理もして
いただきます。
それでは、京間先生、どうぞ」
教頭に手で合図され、CBのライダー、京間が教師たちに向かって頭を下げる。
「京間 郡司です。短い間ではありますが、皆さん、よろしくお願いいたします」
放課後になり、京間は一人の男性教師に連れられ、屋内温水プールへとやって来た。
その教師は、水泳部の副顧問だった。
「本来ならば、私が、監督監視をしなければならないのですが、ちょうど今日から、
研修へと行かなければならないんです。
初日から大変だと思いますが、よろしくお願いいたします」
「ええ。まあ、なんでもやらしていただきます。それが、私の役目ですから」
そして、お決まりの、部員たちを前にしての紹介が終わり、京間は、水泳部員達が、
自主的に練習するのを、プールサイドで黙って見ていた。
内心、
『こりゃあ、楽でいいわ』
などと考えていたものだ。
しばらくは練習風景を眺めたり、部員の資料を見ていたりしたのだが、そのうち、
苦笑いを浮かべながら、頭を振った。
『やれやれ、高校生ってのは、こんなにいい体格してたかな?』
(まあ、その視線の対象が女子だということは、ここでは敢えて伏せておきましょう)
それにしても、と彼は思った。
『そう言えば、今朝のTZRの女もいい体格してたからなあ』
京間は自分の記憶をたどって、今朝方、目に焼きつけた、背中から腰のラインを思い
出していた。
そこへ、一人の競泳用水着を着た女子が、京間の前に立った。
その背中を見た京間は思った。
『そうそう、ちょうど、あんな感じの・・・』
そこまで思った京間は、突然、その女子部員に向かって指を差し、叫んでしまった。
「今朝のティーーゼットアーーール!!」
それは無意識の内だったのだろう。
京間にとって、その背中はそれほどインパクトのある物だったのだ。
そう叫ばれた女子部員も驚いた。
「な、なによ!!」
振り向いたその女子部員、緑の髪を短くしたその部員。
それは、望だった。
望は何が起こったのか判らなかった。この事態を理解するのに、相当の時間を必要と
してしまった。
『ちょ、ちょっと待ってよ。なんでTZRって名前がここで出るのよ!?』
そして、一つの過程に行き着いた時、望は京間を指で差し返していた。
「今朝のCB!?」
望の声もかなり大きな物になってしまっていたので、”何事か?”とプールにいた人
間の注目を浴びてしまった。
その視線に気付いた望は、京間の腕を取り、半ば無理やりに引きずるように、プール
から死角になったところへ連れて行った。
「ちょ、ちょっと。どういう事よ、これ?」
必死の形相で聞いた望だったが、京間の方は平然としたものだった。
「いやあ、これも運命って奴だと思うよ」
「そんな事じゃなくて、どうして判ったの? 私が、今朝のTZRだって?」
望の言葉使いは、教師に対するものではなく、同じバイク乗りに対するものになって
いた。
「ん? いや何、その力強そうな腰付きで、一発だったよ」
「!?」
焦ったように腰に両手を当て、望は顔を赤らめる。
「こ、この、セク・・・」
「セクハラはやめてくれよな。一応、俺にも婚約者がいるんだ。
それに、あんなに見事なコーナーリングを見せられりゃ、嫌でも憶えるぜ。
その背中はな。
君はそうじゃないのか?」
ウインクをしてそう言った京間に、望は毒気を抜かれた感じになった。
「わかったよ。
ところで、この事は内緒にしておいてくれよな。
他の部員たちは知らないことなんだから」
「なんで?」
「なんでって、片手間に水泳してると思われたら嫌じゃないか!」
京間は首を傾げる
「片手間なの?」
「馬鹿言わないでよ!
一生懸命やってるわよ!!」
「だったらいいじゃない」
望は反論に一瞬の間を置いてしまった。京間は笑いながら言った。
「まあ、君がそう言うなら内緒にしておこうか。
・・・ところで、まだ、名前を聞いていなかったよね?」
「え? ああ、私は清川 望。3年生」
京間は、それを聞いていぶかしげな表情になった。
「どうしたの?」
「その名前、・・・どこかで・・・」
「水泳雑誌か、なんかじゃないの?」
しかし、京間は首を振ってそれを否定する。
「いや、違うな・・・、清川、清川・・・キヨカワ・・・?
キヨカワレーシング!?」
「あっちゃーーー!」
望は額に右手を当て、嘆いた。
「思い出しちゃったか」
「やっぱり、そう!?」
観念したように、望はうなだれ答える。
「そう、キヨカワレーシングは、お父さんのチームだよ」
「そしてお祖父さんは、生きた伝説と呼ばれる、”キース清川”!!」
「やめてよ。おじいちゃん、そのニックネーム嫌いなんだって言ってたもの。
”俺には喜助と言う名前がある”って」
「まあ、そのエピソードは有名だけどな。
しかし、ヨシムラ、モリワキ、そしてキヨカワと呼ばれる、日本を代表するチューナ
ー、キヨカワの・・・娘さんなのか?」
「そうだよ。だから、みんなには内緒だよ。お願い」
そう言って、望は顔の前で両手を合わせる。
「それはいいけど、・・・でも、なんで?
なんで、水泳なんかやってるの?」
「ま、これにはいろいろと事情が・・・」
「あるんだろうねぇ。
もちろん聞かせてくれるんだろうねぇ?」
「えーーっ!?」
望はそう言ったが、京間の意地の悪そうな表情を見て、あきらめたような表情になっ
た。
「判ったよ。話すよ。ただし、練習が終わったらね」
「はいはい、それでいいですよ」
「じゃあ、練習に行くから。くれぐれも・・・」
「秘密にしておく・・・だろ?」
「頼むね」
そう言ってプールに戻り、泳ぎ始めた望を見ながら、京間は思った。
『こりゃあ、ひょっとすると、今までの中で一番楽しめることになりそうだな。
一発、やってみるかな?今年の4耐』
その京間の顔は、どう見てもいたずらっ子のような表情になっていた。
(良いのかそれで?)
to be continue RZM「3」
SS RZM(3)251-Line
第3回 「鈴鹿4時間耐久レース」
水泳部の練習が終わり、室内プールの質素なロビーで(さすがに高校で会員制のプー
ルのような物はない)、ベンチに腰掛けながら、望と臨時講師の京間は話し込んでい
た。
京間は、驚きを隠しきれないと言った表情で、望の話を聞いていた。
望は、幼い頃からオートバイなどのレースに、深く関係する環境の中で育った。
オートバイの部品などは、望にとっておもちゃ代わりであったし、人形遊びをするよ
り、バイクを触ってる方が早かった。
さらに、どうしても、その周りに集まってくるのは男性が多くなるので、言葉遣いや
物腰が、男性のようになってしまった訳だ。
(親はそれを嘆いたこともあったが、自分たちがその環境を生み出してるんだから、何
も言えないんだね)
ともかく、そんな環境で育った望は、ごく自然にオートバイのレースなどに参加する
ようになってしまった。
両親も反対せずに、むしろその手助けをするぐらいなのだ(特に父親!)。
幼児用のポケットバイクから始まって、免許が取れない年齢でも参加できる大会や、
クローズドレースなどに出て、その速さを発揮するようになっていた。
だが、望には不満があった。
レースに勝っても、影で言われる、
「マシンがいいからだよ」
という言葉。それは単なるひがみにしかすぎないだろう。だが、言われた望にすれば、
『私だって、頑張ってるのに』
そう思ってしまうのも無理はなかった。
「そこで出会ったのが水泳と言うわけか?」
京間の言葉に、望はうなずく。
「小学校6年の時、学校の水泳大会があって、そこで勝っちゃったんだ。
それで、地区の大会の選手に選ばれて」
「あれよあれよと、勝ち進んでしまったわけだ」
「うん、そうなんだ」
京間は天井を見上げため息をついた。
「まあ、小学校ぐらいだと基礎体力がものを言うからなあ。バイクに乗るために身体を
鍛えていたのが影響したんだな」
「そうだろうね・・・。
それで、その時思ったんだ。
水泳は体一つの勝負。マシンのハンデなんか関係ない。結果は全て自分に帰ってく
る。
そう思ったら、どんどん、水泳にのめり込んでしまって・・・」
「そして、現在に至る・・・という事か」
「うん」
望はにっこりと微笑んで、そう答えた。
京間はそれを聞いて、ぽつりと言った。
「でも、バイクもやめられなかった。・・・峠での、あの走りからすると、今でもやって
るんだろ? バイクは?」
「うん。あの風を切る感覚は、一度体験したら忘れられないよ」
「だろうな。それは判る。・・・しかし、大変だろ、両立は?」
苦笑いのような笑顔で、京間は望に聞いた。
望もコクリとうなずく。
「正直言えば大変だよ。でも、自分が好きでやってることだから、全然苦にはならない
よ」
「それで、どうなの? 公式レースなんかには出ないのかい?」
京間の問いに、首を傾けながら望は答える。
「どうかな? 出てみたいって言うのはあるよ。でもなあ、機会もないし、お父さんの
チームから出場するって言うのも、あまり意味がないしなあ」
「なんで?」
「だって、親の七光りって思われるのって、癪じゃない」
「そんなもんかなあ?」
「そんなものなのよ」
「ふーーん」
京間はそう言って、手を頭の後ろに組む。そして、しばらくの間を置いて、笑いを浮
かべながら、望に聞いた。もっとも、その笑い顔は、いたずら小僧が浮かべる笑いと、
さして違いのない類の物だったのだが。
「それじゃあ、キヨカワと全く関係のないラインで、レースに出られる機会があったら
走るかい?」
「え?」
思わず、そう言ったきり、望は考え込んでしまった。京間の言おうとしている事が、
今一つ理解できなかったからだ。
「それ、どういう意味?」
ようやくそう聞き返した望に、京間は胸を張って答える。
「俺のチームで、この夏の鈴鹿4時間耐久に出ないか?」
望は、すぐには答えなかった。と言うより状況が掴めなかったと言うべきか?
「・・・そ、それって、どういう事?」
「いやあ、俺のチームって言ったって、まだ何も決まってなくて、やろうかなあ、と思
っていただけなんだ」
「あら?」
少々、間の抜けた答えに、望はずっこけた。
そんな望を見て、京間は慌てる素振りも見せず、淡々と続ける。
「だけど、清川さんのようなライダーが加わってくれるのなら、具体的に行動を起こし
てみようかなと考えるんだよ。
どうかな?」
「どうかな?って言ったって、そんなに突然言われたって、すぐに答えられないよ。
それに、具体的に行動を起こすって言ったって、何をどうするのさ?」
京間は腕を組み『よくぞ聞いてくれました』とでも言うかのような表情を浮かべる。
「資金は、こつこつ貯めてきたのがある。豊潤とは言えないけど、初期資金としてはな
んとかなるだろう。
メカニックは一応コネがあるからなんとかなるんだが、ライダーだけが決まってなか
ったんだ。そこに、清川さんが現れたと言うわけだ。
これを運命と呼ばずして何としよう」
京間は本当に嬉しそうな表情を浮かべていた。
望は半ば呆れるような表情で、首を振りながら言った。
「私と・・・えーーと。・・・」
「きょうま ぐんじ」
「ああ、京間・・・先生とでライダーをすると言うわけ?」
「いや、俺は出られない」
「なんで?」
「俺、一応、国際A級持ってるんだよ」
今度の京間は、照れたような笑いになっていた。
だが、望は相当に驚いてしまった。
「な、なんですってぇ!?」
京間を指さし、望は絶句してしまった。
鈴鹿4時間耐久レース(通称4耐)。
一般にも相当に有名になっている、鈴鹿8時間耐久レース(通称8耐)の前日、すな
わち土曜日に行われる、いわばサポートレースだ。
だが、モーターレースに「参加」する人々からすると、鈴鹿8時間耐久レースより、
はるかに身近に感じるレースであったりする。
鈴鹿8時間耐久レースは、世界耐久選手権に組み込まれているところからしても、そ
のレベルは相当に高く、おいそれと参加できるものではない。
ライダーの参加資格からして、国際ライセンス保持者に限定されるぐらいなのだ。
また、国内のワークス(要するにオートバイメーカー)がぶつかり合うこともあって
「世界でもっとも熱い耐久レース」とさえ言われるほどで、予選を突破するだけでも、
資金、ライダー、技術力、マシンの戦闘力、どれを取っても相当な物となっているので
ある。
その点、4時間耐久レースは、はるかに敷居が低い。
ライダーの参加資格も、国際ライセンス保持者は、逆に出場できない程で、野球に例
えるならば、鈴鹿8時間耐久レースがプロ野球であり、4時間耐久は高校野球、と言う
所だろう。
「バイク野郎の甲子園」
それが鈴鹿4時間耐久レースなのだ。
(でも、このコピー、ちょっと恥ずかしいよなあ)
驚きと同時に、呆れたような成分を含ませながら、望は京間に聞いた。
「な、なんで? なんで、先生やってるの!?」
「レースじゃ、めしは食えないからね」
いともあっさりと、京間はそう答えた。
「大学の頃、夢中になってライセンスを取るところまでいったけど、卒業したら、そう
もしてられなくなってね。
まあ、清川さんのような人には、夢のない話で申し訳ないんだが」
「ううん。私もそういう事、わかるから」
華やかに見えるモータースポーツだが、それで生活するというのは、なかなか出来な
い。
その辺りの事情は、幼い頃からその環境に接してきた望にはよく判る。
「でも、なんで自分で出ないの? 8耐に出ればいいじゃない」
「金がない」
またも、あっさりと答える京間だ。
「マシン、改造、運営、なんでもかんでも、のべつ幕なし金がかかる。
そこへ行くと4耐なら、その負担ははるかに少ないからね。
自分で走りたいのは確かにあるんだが、監督というのもいいんじゃないかなと思って
ね。
まあ、事情はいろいろとあるんだが、それは追々話すとして、・・・どうだい?、やっ
てみないか?」
「ちょっと待ってよ。会ってそうそう、そんな話をされたって答えようがないよ。確か
におもしろそうな話だけど、こっちにだって事情があるんだから!」
「まあ、そりゃそうだな」
「ともかく今日は遅いし、家に帰って考えてみるよ。まだ聞きたいこともあるし。
それでいいだろ?」
「ま、当然だよな。色よい返事を待ってるよ」
京間は納得したように、うなずきながら言った。望は自分の荷物を手にとる。
「それじゃ、帰るよ」
「はいはい」
そうして室内プールを後にしながら、望は思った。
『なんだか、妙な事になってきたなあ』
ちょうどその頃、公は下校しようと、校内の駐車場を歩いていた。
「たく、先生も、何かって言うと、すぐに俺に雑用を押しつけるんだもんな。
すっかり遅くなっちゃったな」
夕闇が訪れ、暗くなりつつある中を公は歩いていた。
「公くん」
そんな公を呼び止める者がいた。
「詩織、部活終わったの?」
「うん。・・・あのね、よかったら、一緒に帰らない?」
「ああ、いいよ」
彼を呼び止めた女子生徒、名前は藤崎詩織。公とは、家が隣同士の幼馴染みである。
そして、その名前は、きらめき高校に、肯定的な意味で、広く知れ渡っている。
きらめき高校のマドンナと呼ばれるほどの容姿、成績も優秀で、性格も良く、誰から
も好かれる彼女が、校内の人気を集めることは、ある意味当然のことだった。
二人が連れだって歩き出そうとした時、公は駐車場の雰囲気が、今までとは違うこと
に気が付いた。正確に言うなら、そこに置いてあるバイクに気が付いたのである。
「あれ? あんなバイク、誰が乗ってたっけ?」
まるで夢遊病者のように、そう言って、公はそのバイクに近付いていった。
「ちょ、ちょっと公くん。帰るんでしょ?」
慌てた口調の詩織に呼び止められて、公は我に帰る。
「あ! ごめん、ごめん。・・・でも、ちょっとだけ、いいだろ?」
「んもう。しょうがないなあ。ちょっとだけよ」
「ああ、判ってるって」
ウインクして公はそう答え、バイクに近付く。
「CB400スーパーフォアか。 いいなあ。レーサーレプリカもいいけど、こういう
ネイキッドも捨て難いなあ」
「本当に、公くんって、オートバイが好きなのね」
「ああ、大好きなんだよ。早く大手を振って乗れるようになりたいなあ」
「私と、どっちが・・・」
「え? なんだって?」
「ううん。なんでもないの。
ところで、このオートバイ、HONDAなのね。私、前まではHONDAって車の
メーカーかと思ってたわ。オートバイも作ってるのよね」
『バイクだって車なんだけどなあ。それに、HONDAは2輪から始まったのに』
などと考えながら、公は苦笑いを浮かべて、詩織の感想に答える。
「他にも4輪と2輪を作ってるメーカーはあるんだよ」
「あ! うん、それ知ってるわよ。BMWでしょ。SUZUKIでしょ。TOYOTA
よね?・・・あれ?違ったかしら?」
頭を抱えた公の姿に、詩織は自分が間違えた事を言ったのか、と思った。
「BMWを知ってるのは、すごいよ。さすがは詩織だって思うけど、・・・TOYOTA
は、・・・違うんだよ」
「もう、意地悪!」
詩織は片手を上げて、公に抗議をして見せた。
『公くんったら、本当に意地悪なんだから、どうして私が、そういう事を知っていると
思ってるのよ。
公くんがオートバイを好きだって言うから、なのに』
詩織の心の声が聞こえるはずもない公は、目の前のCBに見とれていた。
「あれ、公くん。どうしたの、こんなところで?」
そう言って呼びかけてきたのは望だった。
「あれ、清川さん」
首だけ横に向けて、公は望に答える。
「いや、このCB、誰のかな? って思ってね」
「ああ、これね。きっと京間って言う、臨時の先生の物だよ」
「清川さん、なんで知ってるの?」
「え? ああ、その、水泳部の臨時の顧問でもあるんだよ、その人」
「へーー、そうなんだ」
公はそう言って、再びCBに視線を向けた。
「こんにちは、清川さん」
「え、ああ、こんにちは、藤崎さん」
この時、二人の互いを見つめる視線がぶつかり合い、見えない火花を散らせた事に、
CBに見とれていた公は「全く」気が付いていない。(苦笑)
望から視線をそらせないまま、詩織は公の腕を取る。
「もう、そろそろ行きましょう。公くん」
「あ。ああ、そうだね。 それじゃあね、清川さん」
「あ! 公くん!」
「え? 何?」
「えっと、・・・や、やっぱり、なんでもないの。それじゃ!」
望はそれだけ言って、駆け出していった。
『どうしたんだろう? 変な清川さん』
その背中を見送りながら、内心でそう思う公だった。
望は自宅の自分の部屋に戻ると、鞄を置き、私服に着替えると、ベッドにその身を投
げ出した。
天井を見上げ、公の顔を思い出しながら、ほんの少し、すねたような口調で言った。
「公くんの馬鹿。私の気持ちも知らないで・・・」
しばらくそのままの姿勢でいた望だったが、不意に飛び起き、部屋を飛び出した。
「こんな時には、あいつの顔を見よう」
そんな独り言と共に、ガレージの奥へとやって来た。
そこにはシートを被せられた、一台のバイクがあった。
望は、そのシートを注意深く取り、そばにしゃがみこむ。そして、そのバイクに向け
て言葉を放つ。
「お前、また、走りたいか?
ひょっとしたら、その機会があるかも知れないよ」
だが、当然のごとく、バイクからの返事はなかった。
to be continue RZM「4」
SS RZM(4)249-Line
週末の土曜日の夕方近く、京間はCBを降りて、ヘルメットを取る。そして、見上げ
た先には、3階建ての建物があった。
「ここが、キヨカワレーシングの総本山というわけか」
ぽつりとそう言って、店先に入る。
「あのー、すみません」
「はい、いらっしゃい」
一人の若い男が京間を出迎える。営業用の笑顔が、まだぎこちない。
「私、きらめき高校で講師をしています、京間と申しますが、お嬢さん、望さんはご在
宅でしょうか?
今日、ここに来るように言われたのですが」
「え? お嬢さん? 学校で何か?」
「いえ、これはプライベートな事で、・・・その、なんて言うか、バイクの事で、相談に乗
ってもらおうと言う事なんです。
決して、心配には及びません」
「・・・そうですか。少々お待ち下さい」
若い男は内線電話で、(恐らく望の部屋なのだろう)一言二言、話した。
「今、いらっしゃいます。お待ちください」
(京間は内心で『敬語は身内で使わないもんだぞ』などと、チェックを入れていた)
金曜日の日、京間は「家に来てくれないか?」と望に言われた。
鈴鹿4時間耐久レースについて、詳しい話をしたいという事だった。
学校では、あまりおおっぴらに話せる話題ではないし、かと言って、外で話し込んで
あらぬ疑いを持たれるのもいやだった。
(京間のアパートに行くというのは問題外)
結局、望の家、バイクショップの店頭ならいいだろう、という事になったのだ。
望が奥の方から現れた。
「お待たせしました。どうぞ、そちらへ」
「ああ、どうも」
バイクなどが展示されているスペースの一角に、カタログなどが並べてある棚と、
テーブル、椅子があり、二人はそこに座った。
「それで、何が聞きたい?」
京間は、ズバリと切り出した。
望もその方が性に合っているらしく、うなずいてから、落ち着いた声で言った。
「そもそも、京間先生が監督となって、4時間耐久に出ようって言う理由は何なの?
まず、それを聞かせてもらいたいな」
「そうだね。清川さんの言う通りだな。それから話そうか」
腕を組み、京間は話し始めた。
京間の話を略すとこうなる。
大学を出た後、京間は定職にも就かず(就くこともままならなかった、と言う事情も
あった。・・・身につまされる話だなあ)親元で、ある程度自由な生活をしていた。
教員資格を持っていたので、教師になることも考えたが、親のコネで、臨時講師にな
るのが精一杯だった。(今回のきらめき高校もそういった口だった)
そんな京間だったが、ご多分に漏れず、一人の女性に恋をした。
その女性も、京間に好意を抱いていたので、二人は付き合う事になったのだが、その
女性には、男の兄弟がいなかった。
そして、その女性の親はある有名予備校の経営者だった。
当初、自分の娘が男と付き合っている事を、快く思っていなかった父親だったが、
京間を知るにつれて、すっかり意気投合してしまい、教員の資格を持っているという事
もあって、自分の娘と結婚して、後継者にしたいと言い出したのだ。
つまり、婿養子というわけである。
京間は、家とかにはこだわらない方だったし、愛情が確かなものであったため、話は
とんとん拍子に進み、この秋、入籍、挙式という段取りになっていたのである。
だが、その前に、独身最後の夏を自分の思う通りにすごしたいと言う、願望があっ
た。
「それが4耐と言う訳?」
黙って話を聞いていた望がそう聞いた。
「まあ、そんなところかな」
京間の返答は、そんな人生の転換期を迎えているとは思えない口調だった。
「ふーーん」
話を聞いた望は、しばらく考え込んでいたが、やがて顔をあげて言った。
「よし、いいよ。やってみようじゃないの」
「え?」
それまで平然としていた京間だったが、望の返答には驚きを隠せなかった。
「ちょ、ちょっと待った。 そんなに簡単に決めちゃっていいの?」
「それじゃあ、もっと悩んでいいのかい?」
「いや、そりゃ、早けりゃそれに越したことはないけど、そんなに簡単に・・・」
望はその声を最後まで続けさせなかった。
「8年前」
「は?」
「鈴鹿8時間耐久レースに新しい歴史が生まれた。並み居るワークスを押しのけて、
大学のチームが優勝したことがあった。関東工技大学自動車部、ライダーは現在、世界
GP500CCクラスで活躍中の、沢田 鷹志」
望がそこまで言った時、京間の表情が明らかに変わった。
「調べたのか?」
「うん。国際ライセンスを持っているって言うから、資料ぐらいあるだろうと思って、
チームの事務局の資料をひっくり返してね」
笑いながらそう言った望に、京間もつられて苦笑いを浮かべる。
「まあ、あの時には話題になったけどね」
「その沢田 鷹志のパートナー、それが京間 郡司。先生のことだよね?」
京間は黙ってうなずいた。
「ここのメカに栗田さんって言う人がいるんだけど、あの時のことはよく憶えているっ
て言うよ」
「あれでタカは、一躍、有名になったからな」
「ううん。栗田さんはそのパートナーのこともよく憶えていたよ。決して、ずば抜けて
速くはなかったけど、クレバーな走りは耐久に向いている。
京間先生がマシンを大事に扱っていたからこそ、あの優勝があったって言ってたよ。
耐久を続けていたら、良いライダーになったはずだとも言ってたな」
望の表情は、冗談や冷やかしなどではなく、芯から尊敬の念を抱いた物になってい
た。
京間は再び苦笑いを浮かべて答えた。
「まあ、その耐久じゃ、食っていけないからね。今の道を選んだわけなんだ。
それに、俺にはタカのような天性の速さはなかったから、あのぐらいが限界だったん
だよ」
「・・・そう、そうなんだ」
望の表情に、わずかな影が差したのを見て、京間は慌てて付け加える。
「念のために言っておくけど、決して後悔している訳じゃないよ。
今の選択は間違っていなかったと思っているからね」
「うん、そうだよね。オートバイだけが道じゃないもんね。それに、その気になれば、
こうして新たにチャレンジできるんだもんね」
「その通りだ。協力してくれるんだね?」
「ああ、いいよ。・・・ただし、条件があるんだけど、聞いてくれるかな?」
「どんな条件だい?」
望は椅子に座り直し、息を一回、大きく吸ってから、その条件を口にした。
「まず、マシンは、私が、「これで出たい」と言う希望があるんだけど、それでいいか
な?」
「・・・、ああ、ライダーの意見を尊重したいからね。それでいいよ。それに、清川さん
ほどの腕なら、めったな事は言わないだろうからね」
「うん、ありがとう」
「それで。”まず”と言うからには、他にもあるんでしょ?条件」
「他の条件というのはね。パートナーのライダー、それにメカニックなどは、私の知り
合いの中から選びたいんだけど、どうかな?
それで間に合わなかったら、先生の手を借りたいんだけど・・・」
今度の条件には、すぐに首を縦には振らない京間だった。
「それは、リスクが大きいぞ。知り合いと言うからには、高校の同級生あたりか?
経験を積んでる訳じゃないだろ?」
それが図星だったため、望はためらうようにして、こくりとうなずいた。
「・・・駄目かな?」
「・・・リスクが大きいというのは、満足に走れなくなるかもしれない。という事で、そ
れを覚悟しているのなら、それでもいいよ」
「ほ、本当に?」
「高校生活での思い出を残したいんだろ? 友達と鈴鹿の思い出を作る。十分な動機だ
と思うけどね。
ただし、清川さんの判断に任せはするけど、あまり無理は言わないでくれよ」
「うん」
「それと、間に合わないと思ったら、早めに言う事。それを頼むよ」
「はい」
「決まりだな。詳しいことはこれから決めるとして、とりあえず、マシンは何にするん
だ?
キヨカワだと、どうしてもGSX(SUZUKI)やFZR(YAMAHA)系を想像してしまうん
だが、わざわざそう言うからには違うんだろ? 何にするつもりなんだ?」
京間の質問に、望は少しためらってから言った。
「実物があるんだ。見てもらった方がいいよ」
望と京間は、2階のフロアに上がり、そのフロアのガレージ奥へとやって来た。
そこにはシートに被われた一台のバイクがあった。
京間はそれを指さし、望に聞いた。
「これ?」
「そうだよ」
短くそう答え、望はシートを取る。
「こ、これは・・・」
京間はしばらくの間、そこから現れたバイクが何なのか判らなかった。
ホイール、チャンバー、果てはフレーム、ほとんどの場所に手が加えられており、自
分の記憶にある、どのバイクにも当てはまらなかったのだ。
だが、白地に青のラインの独特のデザインが施されたタンク、そして誇らしげに貼ら
れた3音叉のステッカーを見た時、ようやくその名前が出てきた。
「・・・RZか?」
「そうだよ。これは82年モデルだけど、基本設計はなんと79年。
当時、一大センセーションを巻き起こした、YAMAHA RZ250。
私はこれで出たいんだ」
京間は何も言わず目の前のRZを見つめていたが、やがてぽつりと言った。
「訳を・・・」
「え? 何?」
「訳を聞かせてもらえるかな? RZを使う訳を」
「反対しないの?」
「これだけ手を加えてあり、清川さんが言うぐらいだから、それなりの戦闘力はあるだ
ろう。それについては反対しないよ。
だけど、苦戦は免れない事は明白だ。それでも、このRZを使うからにはそれなりの
理由があるだろう。それを聞かせてくれる?」
「もちろん、そのつもりだよ」
RZに手を置き、望は続ける。
「このRZはね、私のなんだ。校則で禁じられてるからナンバーは取れないし、ご覧の
通り保安部品も付いてない。サーキットを走るためのバイクなんだ。
そして、私が最初の本格的なレースに出たマシンでもあるんだよ」
京間は納得したような表情を浮かべた。
「なるほどねぇ、思い出のマシンと言う訳だ」
「うん、そうなんだ。家の手伝いをしながら、パーツなどを見つけて、教えてもらいな
がら、手を加えてきたけど、さすがにもう限界だよ。 部品なんかも、なかなか、手に
入らなくなってきたし」
「・・・最後に一花?」
「うん」
力強い望の返事を聞いた京間は、顎に手を当ててしばらく考え込んだ。
そのうち、心配そうな顔の望に気づき、根負けしたと言った表情で首を振った。
「判ったよ。なにはともあれ、ベースのマシンがあると言うのは、資金的にも楽だから
な。それで行こう」
「やったあ」
望の嬉しそうな表情は、京間に笑顔を誘った。
「ところで、メカニックなんかどうするんだ? 心当たりなんかあるのか?」
京間の質問に、望は少しばかり自信なげに答える。
「あるにはあるけど、返事を聞いてからだから、少し待っててよ。
その前に、エンジンに手を加えるつもりなんだ」
「エンジンに? どうやって?」
一転して強気な語気で、望は答える。
「ま、週明けを待っててよ」
「・・・ああ、そうしようか」
一抹の不安を感じつつ、京間はうなずいた。
週が開けた月曜日の昼休み、望は化学部の部室にいた。
「わかったわ。なかなか、面白そうな話ね」
机をはさんで望と向かい合い、椅子に腰掛けていた女子生徒がそう言った。
前髪が、顔の半分を隠そうかと言う程長く、その素顔は、いかにも理知的な物を感じ
させる。
「ほんとにやってくれるの? 紐緒さん?」
「あなたが言ってきたんでしょ? 特定条件下における、内燃機関の限界性能の実験、
および実践と言うテーマは」
「そうそう、その、特定・・・、ええーと」
言葉につまった望に、その紐緒と呼ばれた女子生徒は、言葉を変える。
「古い設計のエンジンを、規則にあわせながら、今の物と遜色のない物とすることが、
出来るかどうか? 面白いテーマだと言うのよ」
彼女の名前は紐緒 結奈。理系がずば抜けた成績の、化学部の部長である。
一年の文化祭の時、結奈自身が「片手間でやった」と言うガソリンエンジンを見た
時、望は驚いた。
それは、とても高校生がしたとは思えないほどの改造で、性能もよかったのだ。
そんな事があって、望は前々から、結奈にエンジンチューンをお願いしようと思って
いたのだが、なかなか、その機会がなかった。
望にとって、科学部の敷居は高かったのだ。
だが、今回、そうとばかりも言っていられず、思いきって交渉に乗り出したのだっ
た。
難航するかと思われたのだが、意外に結奈の良い返事が早かったので「ほんとに」
と言ってしまったのだ。
「ともかく、そのエンジンを持ってきてちょうだい。
詳しいことはそれから決めるから」
「うん、わかったよ。早速手配するから待っててよね」
望は一番難航すると思っていた事が、意外とすんなりいったので、内心、幸先の良い
物を感じていた。
『よーーし。次は、・・・公くんだな』
そう思いながら、両拳に力を込めた望だったのだが、その頬が赤く染まっていたのは
何故なのだろうか?(何故も何もないもんだ)
そのころ、その公は?と言うと、校内の中庭で弁当を食べていた。
その弁当は自分が持ってきたものではなく、その隣にいる青い髪の女子生徒が持って
きたものだった。
「こんなにおいしいお弁当が何度も食べられるなんて、俺は幸せ者だなあ。
虹野さんって、本当にお料理の名人だね」
公に虹野さんと言われたその女子生徒は、頬を赤らめつつ(またか?)答える。
「え? 本当に? 嬉しいなあ。まだまだあるから、どんどん食べてね」
彼女の名前は虹野 沙希。公と同じ3年生である。
サッカー部のマネージャーの彼女は、運動部のアイドルなどと呼ばれるほど、愛らし
い素顔を持っている。
沙希が持ってきた弁当を、公が食べるという構図は、今までにも、何度かあったもの
である。
そんなところへ、望がやって来た。
「あ! 公くん。捜したよ!!・・・?! あれ、虹野さん?」
「あれ? 清川さん。・・・どうしたの?」
この時、詩織と望が発した物ほどではないが、二人の間に発生した、ささやかな、
見えない花火に、弁当に夢中になっていた公は、やはり気付かなかった。
(おまえ、いい加減にしろよ)
to be continue RZM「5」
SS RZM(5)268-Line
第5回 「胎動」
春の陽射しの中、きらめき高校内の中庭には、緊張感とは言えないまでも、一種独特
な雰囲気が醸し出されていた。
芝生の上、公の横に座っていた沙希が、望を見上げながら言った。
「あれ? 清川さん。・・・どうしたの?」
まっすぐに望を見つめる沙希の青い瞳に、訳もなく気押されされるような物を感じつ
つも、望が答える。
「ええと、公くんに用なんだけど・・・」
「でもぉ、今、お食事中なんだけど」
それは決して、そういう口調ではないし、本人もそのつもりはないだろうが、そこか
らは、
『今は駄目』
と言うニュアンスが、取れないこともなかった。
沙希が作ってきた弁当のおかず、海老フライを口にしながら、公が割り込んでくる。
「食べながらで良かったら、聞くけど、何?」
「う、うーーん。・・・やっぱりここじゃ、・・・」
望を知る人間には、彼女の今の様子は、普段とはずいぶん違ったものに見えた。
「何か、良くない話?」
心配げな公の声に、望は首を振りながら答える。
「そ、そう言うわけじゃないんだけど、・・・じゃあ、帰りに店によってね。私も部活が
終わったら、すぐに行くから」
「店?」
そう言ったのは、公ではなく沙希の方だった。望と公の間で「店」と言えば、それは
望の家のバイクショップの事と決まっているのだが、沙希には何のことかわからない。
もっとも、それは沙希だけではなく、望と公だけが判る、一種の暗号の様なものだっ
た。沙希が判らないのも、もっともなのだが、彼女の疑問に、二人とも答えず、公が、
望に答える。
「うん、いいよ。先に行って待ってるから」
「それじゃあね」
望と公の二人だけに判る会話をした後、望はその場を離れた。
「ねえ、公くん。お店って何のこと?」
一人蚊帳の外に置かれた形となった沙希が、遠くなる望の背中を見つめながら公に聞
いた。だが、公は上手く答えることが出来ない。決してやましいことではないが、軽々
しく言って良い事とは、思えなかったのである。
「えーーと、・・・ごめん。これは、例え虹野さんでも、話せないことなんだ。
ごめんね」
箸を持ちながら、公は右の手のひらを、顔の前に立てて謝る。
「ううん。いいのよ。気にしなくても。
どうしても話せない事って、あるもんね」
言葉ではそう言った沙希だったが、内心では
『ああーー、もう、気になるなあ。こんな時、頼りになるのは朝日奈さんよね。
後で聞きに行かなくちゃ』
などと、考えていたのだった。
(これが後々どうなることかな?)
ほぼ同時刻、一人の男子生徒が廊下を歩いていた。茶色の髪を持ち、やや、軽そうな
雰囲気がある。
その男子生徒を呼び止める声があった。
「あ、あの、早乙女くん」
「?・・・ああ、美樹原さん」
早乙女と呼ばれたその男子生徒、フルネームは早乙女好雄と言う。
彼の名前は、校内では知る人ぞ知るという類のものだった。
と言うのは、ともかく情報が早く、正確だったのである。一体どうやって仕入れるの
か? 多くの人間が悩む事になっているのだが、ともかく事実としてそうなっていた。
ただし、その情報が女子生徒に関する物が多かった。という事が付け加えられるのだ
が・・・。
その好雄を呼び止めたのは、滑らかな栗色の髪を持った女子生徒だった。
名前を美樹原 愛。
言葉を選ばずに言えば、校内でも目立たない、おとなしい娘だ。
その愛が、好雄に聞く。
「あ、あの、詩織ちゃん、知らない?」
「藤崎さん? ・・・えーと、確か、図書館に行くと言ってたよ。何だか知らないけど、
調べ物があるんだって」
「あ、そうなんですか・・・」
そう言って、何か言いたげにもじもじしていた愛に、好雄が言った。
「一緒に行こうか? 図書館」
「え?」
「藤崎さんに用があるんでしょ? 一緒に行こうよ」
「は、はい、そうですね。行きましょ」
嬉しそうに微笑みながら、愛は答えた。
好雄の言った通り、詩織は図書館で、何事か調べている風だった。
邪魔にならないように、二人は静かに、詩織のいる机の椅子に腰を下ろした。
「あら? メグに早乙女くん、どうしたの?」
二人に気付いた詩織が、小声で言った。
「俺の方には、特に用というのはないんだけど、美樹原さんが藤崎さんに用があるみた
いなんだ。
俺はそれに付いて来ただけ」
やはり小声で、好雄が答える。愛がそれに続く。
「私も、特にこれというわけじゃないの。ただ、詩織ちゃん、今日の帰り、時間あるか
な?って思ったの」
「今日? ・・・特に予定はないけど、それが?」
「なら、お買い物と言うか、お使いに付き合ってくれないかな?」
「うん、いいわよ。 でもメグ」
「ん?」
「せっかく早乙女くんがいるんだから、彼に頼めばいいじゃない」
笑いながらそう言った、詩織の声にこめられた意味を感じた愛は、声につまり、俯き
黙りこくってしまった。
内心では、
『ばかばか、詩織ちゃんの意地悪! 早乙女くんの目の前でそんな事言わなくたって、
いいじゃないの』
などと思っていた。
もう一報の当事者、好雄の方も、顔を真っ赤にしながらも、静かに反論した。
「ちょっと、藤崎さん! いくら冗談でも、そんな事言ったら、美樹原さんに迷惑が、
かかっちゃうじゃない。お願いしますよ」
「はい、以後気をつけます」
神妙な面持ちでそう答えた詩織だったが、本当にそう思っているのかどうかは、いさ
さか、心もとない。
何しろ、愛が好雄に好意を寄せているというのは、見た目にもはっきりと判ってい
た。また、好雄の方も、決してまんざらでもないと言うのが、見え見えだった。
そこを詩織は冷やかしたのだ。
顔を真っ赤にしながら、話題を変えようと愛が詩織が見ていた本のことに触れる。
「何を見てるの、詩織ちゃん?」
詩織は自分の手許を見て、その後まわりを見渡してから言った。
「あっちの談話コーナーの方に行こうか?」
図書館の一角に話し合いが出来るスペースがある。
詩織、愛、好雄の3人はそこで話し込んだ。
「それじゃあ、公の奴に言われたから調べてるの? 藤崎さんは」
「だってぇ、公くんったら、私がオートバイのことを知らないからって、馬鹿にするか
ら、悔しいんだもん」
詩織が調べていたのは、オートバイの事についてだった。
先日、バイクの事で公の前で間違ったことを言ってしまい、恥ずかしい思いをしたた
め、今調べていたというわけである。
「ふーーん。詩織ちゃん、公くんの趣味を調べてるんだね」
そう言った愛の口調は、少しばかり意地悪なものになっていたため、詩織の表情が変
わる。
「!? ・・・もう、メグったら!」
そう言った詩織の耳元で、愛が小声で言った。
「さっきのお返しよ」
そう言われては、詩織にも返す言葉がない。『仕方がないなぁ』といった顔で、好雄
の方に聞いた。
「ところで、早乙女くんもオートバイには興味があるんでしょ?」
「え? まあ、ある事は間違いないけど、それが何か?」
「公くんが言っていたんだけど、オートバイに乗ってる人に、新沼健治って人がいるん
だってね?」
「・・・藤崎さん。それ、ニール マッケンジーだよ」
空気が固まった。(お約束だよ。それ)
その日の夕方、公は望の家のバイクショップにいた。
「公くん、バイクを買う資金の方はどうなってるの?」
店の人間にそう言われ、公が答える。公はすでに顔なじみになっていたのである。
「ええ、なんとか貯めてますよ」
「予算を言ってくれれば、いいのを捜すからね」
「その時にはお願いしますよ」
そんな会話をしているところに、望が帰ってきた。
「ごめんね。お待たせ」
「あ、お帰りなさい」
「じゃあ、遅くなってもいけないから、早速用件に入ろうね」
「そうだね」
そうして、ショップの一角で、二人は話し込んだ。
そのうち公が叫ぶ。
「鈴鹿4時間耐久レースに!? 俺が!?」
慌てると言うほどではないが、それでも公の声には、平静さが欠けていた。
「ちょ、ちょっと待ってよ、清川さん。本気で言ってるの? 俺、まだ、ライセンス
取ったばかりなんだよ。
いきなり4耐だなんて」
望は真剣な表情で答える。
「本来、4耐と言うのは、そういうレースなんだよ。
やたらビッグイベントになってしまったけど、レース経験の浅い人達にも参加出来る
耐久レースと言うのが、本来の4耐の趣旨なんだ。
別に、公くんが出てもおかしくはないんだよ」
「でも、清川さんに迷惑かけちゃうかも知れないだろ?」
公の表情は、相当、焦った物になっていた。
「・・・いやなの?」
望の悲しげな声に、公は戸惑う。
「いや、とかじゃないんだよ。清川さん程の人なら、もっとレベルの高い人と組まな
きゃ駄目だよ。
チームになら、それに見合う人がいるでしょ?」
「私は公くんと走りたいの! チームとは関係無いの!」
そう言った後、望は『しまった』と思った。勢いにまかせて言ってしまったが、これ
では告白した様なものだ。
焦る望は、すぐさま付け加える。
「あ! えっと、その、高校の思い出に、みんなで鈴鹿に行きたいんだよ。
そんな思い出って、なかなか持てないでしょ? そんな中でライセンスを持っている
のは公くんだけだから・・・」
正直言って、こんな事でごまかせると望は思っていなかったが、公はそれを素直に受
け取っていた。
「そうか・・・、きらめき高校生でライセンスを持っている人が、他にいるという話は、
聞かないからなあ」
そう言った公の台詞に、望は内心、
『あーーん、この人は、本当にもう!』
と思っていた。(女心は複雑です)
そんな望の思いを知るはずもない公は、自分の言った言葉を、自ら否定する。
「でも、やっぱり駄目だよ。俺じゃ、清川さんの足を引っ張るだけだよ!」
「公くん・・・」
公の強い口調に、望は言葉を無くした。
「望さん、主人君の言う通りですよ」
会話が途切れた、二人の間に声が割り込んできた。
「栗田さん」
「栗田さん」
公と望が同時に声を上げる。
二人がついていたテーブルの脇に栗田が立っていた。
「先日、きらめき高校の先生という方が見えられた時から、望さんが何か動いていると
いうことは知っていました。
その内容も、今日、話が耳に入って大体のことは判りました。
高校のお友達と、鈴鹿4時間耐久レースに出たいというお気持ちは、判らないでもあ
りません。
ですが、望さんには、主人君が言うように、それに見合うパートナーが必要です。
有り体に言って、主人君を望さんのパートナーとしてみた場合、全くの力不足です。
他の人にするべきです」
「ぐ!」
公は唇を噛んだ。自分でも判っていることではあるが、第3者にこうまで言われて、
悔しくない訳がない。
「栗田さん! そんな言い方ってないよ! 公くんがこの数カ月、一生懸命勉強してき
たことは栗田さんだって知ってるでしょ!? 酷いよ、栗田さん!」
栗田に反論したのは望だった。だが、栗田は動じない。
「それが、望さんのためです。所詮、主人君と望さんでは速さの次元が違います。
同じマシンで走る耐久レースでは、百害あって一利無しです」
「栗田さん・・・」
「清川さん!」
反論しかけた望を制したのは公だった。公は立ち上がり、栗田に向き直る。
「栗田さんの言う通り、俺と清川さんじゃ、速さの次元は違いますよ。でも、そうまで
言われて、ハイそうですかとは引き下がれませんよ。
耐久まで、約3カ月しかないけど、それまでに、清川さんのパートナーになって見せ
ます!!
それなら文句はないでしょう!!」
「まだ、レースにも満足に出たことのない君に、それが出来ますか?」
「やってみせます!」
それは普段の公からは想像できないような、気迫に満ちた表情だった。
「・・・公くん・・・」
心配そうに声をかけた望に、公は振り返る。
「清川さん・・・」
「?」
「俺、走るよ。清川さんのために走るよ」
「・・・公くん」
そう言った望の緑色をふくんだ瞳は、涙に潤んでいた。
『遅くなってはいけないから』と言って公が帰ると、望は恐る恐るといった風に、栗田
に聞いた。
「黙ってこう言う話を進めていたこと、怒ってるんですか?」
「なぜ、私が怒るんです?」
「だって、栗田さんがあんな言い方をするなんて・・・。
私、あんな栗田さん見たことないもん。
・・・やっぱり、公くんと走るのは反対なんですか?」
栗田は望の質問に、苦笑いを浮かべる。
「彼が私に言われて、そのまま引き下がるようなら、絶対に望さんと同じマシンには乗
せません。しかし、彼は違いました。
それで、十分です」
栗田の言葉の意味を、数瞬の時を要して、望は理解した。
「そ、それじゃ、わざとあんな言い方をしたの?」
「私は、ライダーに必要なのは、まず闘争心だと思っています。
彼にはそれがあるようです。それに彼は、普段、ぼーっとしてるようですが、いざと
いう時に、どんな可能性を持っているのか? 実は私は楽しみにしているのですよ。
技術や、センスといったものは乗ってみないと判りません。
まずはそれからですよ」
「それじゃ、許してくれるんですね?」
「ええ。ただし、条件が一つ」
「?」
「私もチームの一員に加えてください。老いぼれてはいますが、まだまだ望さんのお力
にはなれますぞ」
「え? そ、それはありがたいけど・・・」
「キヨカワに関係のないところで走りたい、というのでしょう? しかし、メカニック
はどうするおつもりです?
私のような者が一人いれば、ずいぶん違うと思いますが・・・?」
「・・・」
「私もキヨカワの人間という立場から、一時離れます。
望さんのおむつの頃から知っている、口やかましい爺として、加わります。
それならよろしいでしょう?」
おむつ、などと言われて、望の頬が恥ずかしさに赤く染まるが、すぐに真剣な表情に
なる。
「判りました。こちらの方こそよろしくお願いいたします」
そうして二人は握手を交わした。
それは二人にとって、チームメイトという、初めての立場での握手だった。
こうして、鈴鹿4時間耐久レースへの計画は、急速に現実味を帯びていったのであ
る。
to be continue RZM「6」
(第2集)