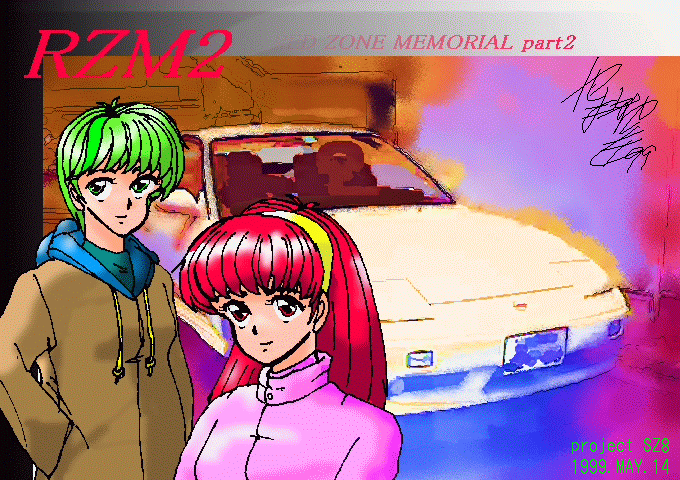
鈴鹿4時間耐久レースの激闘から、4カ月あまり。 初冬を迎えていたこのきらめき市に、今、新たなる最速伝説が生まれようとしてい た。 Welcome Ridge Racer 第1回「白の180SX」 木枯らしが、冬の香りを含ませながら教室の窓を叩く、きらめき高校のある日の放課 後。望は公のクラスを訪ねていた。 「こ、う、く、ん」 望がいかにも故意に、一文字一文字区切って自分の名前を呼んだので、公としても気 になる。 「あれ、どうしたの? 清川さん」 公の質問にすぐには答えず、手にしたカード状の物を、公に見せる。 「じゃーーん!」 そのカードのデザインには、公も見覚えがある。 「なんだ、免許証じゃない。 ・・・ああ、そうか、解禁だもんな」 きらめき高校では、3年生の12月になると、免許証を持つことは自由になる。もち ろん、満18歳にならないと法的には免許は取れないが、仮免許までは取ることが出来 る。 就職活動等の影響を考えてのことで、自動車学校へ行くことも自由になる。逆に、自 動車学校の案内や斡旋をするぐらいなのである。 公はそれを知っていたので、望が免許証が自由に持てることが嬉しくてそんな事をす るんだと、勝手に思い込んでしまったのである。 もともと、望は限定解除の自動2輪免許の保持者だ。だが、校則のせいで、学校へ堂 々と免許証を持ってこれなかったのである。それが解禁となれば、嬉しいのも当然と言 えば当然だろう。 だが、今の望はそうではなかった。 じれったそうな表情をしながら、さらに言った。 「んもう、よく見てよ、ここ!」 「え?」 望が指差したのは免許証の右下だった。そこには取得した免許の種類が表示されてい る。さらに細かく望が指し示した部分、そこに、表示されていたのは、「普通」の上に 書かれていた数字の「1」であった。 自動二輪(中型限定だけど ・・・)の免許を持っている公には、その意味が判る。 「清川さん、普通免許取ったの?」 ようやく、自分の言いたいことが伝わって、望は満足げにうなずく。 「うん、いいでしょ?」 「うん、いいね。 ・・・でも、清川さん、3日前に18になったばかりでしょ? 仮免ま で取ってたとしても、随分早いけど? そう言えば、自動車学校に行っていた風には見えなかったけどなあ?」 公の質問に、望は照れ臭そうに頬を指でかいた。 「う、うん。自動車学校には行かなかったんだ。試験場で直接取ったんだ、一回目で」 「ふーーん、そうなのか ・・・え? ええっ!?」 公が驚くのも無理はない。 一般的になった自動車免許だが、試験場で直接試験を受けて取れるような、簡単なも のではない。 通常は自動車学校に通って取得するのが、ごくごく普通のことであるのだから。 驚きつつも、「清川さんなら、それもありかな?」と公は思った。長い間、自動2輪 で走ってきたこともあるし、そもそも望の運動神経には定評がある。 公は納得しながらも、こう言わずにはいられなかった。 「さすが、清川さんだね。でも、技能試験って難しいんでしょ? よく取れたね?」 「あ、う、うん。私の場合は、技能試験より、学科試験のほうが苦労させられたんだ」 そう言って頭をかいた望に、公はひきつった笑いを浮かべるのだった。 「あ、そ、そう。ははははは・・・ 」 (清川さんの名誉のために説明しよう。通常、軽く見られがちの学科試験だが、自動車 学校に通わずに受ければ、かなり難しいものである) 「ところで公くん。話はこれだけじゃないのよ」 「え? なに?」 「今度の日曜日、空いているかな?」 「空いてるけど、何?」 「それなら、私ときらめき峠に走りにいかない?」 「え? 俺、まだ、バイク持ってないよ」 自分の言葉が足りなかったことに気づき、望は言葉を付け加える。 「ああ、そうじゃなくて、知り合いの人が車を安く譲ってくれたんだ。 それで、一緒に乗っていって欲しいなって思ったんだけど、・・・ だめかな?」 「うん、いいね。行こう」 「本当?」 「ああ。それじゃあ、どうしようか?」 「私、4輪はほとんど初心者だから、他の人に迷惑かけたくないから、朝、早くでかけ ようよ?」 それは公にとっては、いかにも望らしい提案だった。公は納得したようにうなずきな がら、望に聞いた。 「じゃあ、どうするの?」 「うん。朝3時に、公くんの家の前に迎えに行くよ」 「は?」 『 ・・・それって、朝じゃないと思うよ。清川さん』 公はそう思いはしたが、口にはしなかった。 「ところで、今日、藤崎さんはもう帰ったの?」 望の意外とも言える話の展開に驚きつつも、公は答える。 「うん、家の手伝いがあるんだって。 クラブ活動も一段落だし、今日は早めに帰ったよ。 ・・・それが、なに?」 「え? や、やっぱり、なんでもないの。それじゃ、今度の日曜日にね」 そう言って望は走り去っていった。公の返事も聞かずに・・・ 。 (もっとも、公は断りはしないのだが・・・ ) 約束の日曜日の、”朝”3時、公は自宅の前に立っていた。望を待っているのだが、 寒いし眠い。(当たり前といえば当たり前) 寒さに手をこすり、寝ぼけ眼をこすりながらも、望が来るのを待っていた。 すると、夜明け(はるか)前の闇に、1台のエンジンサウンドが聞こえてきたかと思 うと、それが近づいてくるのが判った。 『お、来たな』 公がそのサウンドが聞こえてくる方向に目を向けると、光る2つのヘッドライトが、 こちらに向かってきた。 地面から響き渡るかのようなエンジン音は、その持っている馬力を雄弁に物語ってい るようだった。 「スカイラインRS」 公は思わず口に出した。 街灯に浮かぶ、赤と黒のツートンカラー。特徴的な角ばったロングノーズのシルエッ ト。そしてドアの下部に白字で書かれた DOHC TURBO RSのロゴ。 それは発売当時、センセーションを巻き起こした「日産スカイラインRS」に間違い なかった。(しかもターボ) 「お待たせ。寒かったでしょ?」 助手席のドアを開け、望が言った。 「う、うん。さすがにね」 そう言いながら、公は助手席に乗り込む。 室内は「ヒーター」が効いており、公は一息つく。(実は後になって望が言ったのだ が、このRSにはエアコンがないのだ! はずしちゃったそうなんです) 「それじゃ、行こうか」 「うん。そうだね」 公がそう答えると、望はクラッチをミートさせ、RSを「静かに」発進させた。 「でもすごいね。形式が古いと言っても、スカイラインのRSなんて、なかなか手に入 れられないでしょ? いや、逆に車自体が少なくなってるから、よけい難しいかな?」 目的地のきらめき峠に向かう途中、室内を眺め回しながら、公は言った。 形式が古いため、さすがに新車とはとても言えない車内だが、とても程度がよく、変 に手を加えたような跡がない。 前のオーナーが大事に使っていたことがうかがえる。 「うん。お店の古くからのお得意さんが、私が自動車免許を取るって聞いて”もう乗ら ないから、車検取って、これに乗ったら”って、ほとんど、ただみたいな値段で譲って くれたんだ。 もっとも、車検を取り直したから、税金や保険料なんかが大変だったけどね」 「工賃とか、部品代だって大変だったでしょ?」 「ああ、部品は解体屋さんにつてがあったから、それほどでもなかったよ。 それに工賃って言っても、ほとんど自分で車検通したね」 「へ?」 「細かなところはいろいろ違うけど、2輪も4輪も、車検の取り方なんて覚えてしまえ ば簡単だからね」 望は平然と笑ってそう言ったのだが、公は絶句するしかない。 「清川さん・・・」 (清川さん・・・) きらめき峠は、きらめき市郊外にある。小高い山を越えるスカイラインを総称して、 そう呼ばれる。(この場合、スカイラインとは道のことです。念のため) スカイラインと言うだけあって、その全長は長く、コーナーの数、種類は、豊富であ る。 その頂上付近には観光ホテルや、レストラン、展望台などがありきらめき市における 観光名所ともなっていた。 観光道路と言うこともあり、家族連れや、行楽の車で賑わうのだが、時間帯を選べば 本当に空いており、走りやすい道である。 それを車好きが放っておくはずがない。きらめき峠は、この近辺の走り屋のメッカと なっていた。 実際、望も整備されたバイクの公道テストをする時などは、ここを利用している。 その、きらめき峠に向かう途中、大きくあくびをした公に、望が聞いた。 「眠いの? 公くん」 「う、うん。ちょっとね」 「早起きだったから、無理もないよ」 望はそう言ったのだが、公は内心思った。 『早起きって言う、レベルじゃないと思うなあ』 (確かに・・・ ) 「私はちゃんと寝たから、運転のほうの心配しないでね」 「ちゃんと寝たって、何時に寝たの? 何時に起きたの?」 「うーーんと、夕べは7時ごろには、もうベッドに入ってたなあ。 起きたのは1時半ごろかな?」 「・・・」 公は言葉も出せない。なにしろ1時半といえば、下手をすれば、普段の公が寝る時間 である。 そんな公の思いを知りもせずに、望は続ける。 「でも、公くんの家が、きらめき峠のふもと付近でよかったな。全然逆方向だったら、 もっと早く起きなきゃいけなかったからね。さすがに、これ以上早く起きるのは、私も つらいから」 『これ以上早くなったら、早起きじゃないよ』 苦笑と共に公は思った。 (同じく・・・ ) 二人の乗ったスカイラインは、望の滑らかとも言える、巧みなドライビングによって きらめき峠を駆け上がっていった。 「清川さんって、運転うまいね。とても免許取り立てとは思えないよ」 何気なく言った公の言葉に、望は照れたような笑いを浮かべる。 「え? そ、そうかなぁ? えへへ」 「そうだよ。やっぱり、バイクに乗っていたから、4輪にのっても応用がきくのかな? まさか、無免許で乗ってたなんて事はないよね? いくら何でも」 公は冗談のつもりだったのだが、望の表情がヒクっとひきつる。 「えへへへ、ま、いいじゃない。今となったら、ね?」 「き、清川さん? ・・・やっぱり?」 「う、うん。まあ、ほんのちょっとね」 『”ちょっと”じゃないだろうな、実際は』 公はそう思った。 (まずいよ。それって、やっぱり) そして、幾度となく峠を上り下りしたスカイラインだった。 上りと言わず下りと言わず、そのスピードは上がっていき、公は何度も背中に冷たい 汗を流した。 だが、それは、まだ序の口にすぎなかった。 「よし、だいたい判ったぞ」 「へ?」 公が、そんな間の抜けた返事をしていると、スカイラインは加速しながら、やや、R のきつい、右コーナーへ進入する。 「ちょ、ちょっと、清川さん!ブレーキ!ブレーキ!!」 あまりのスピードでコーナーに進入したスカイラインに、公はブレーキングミスだと 直感した。 その刹那、ハードブレーキングによって、前輪に荷重のかけられたスカイラインは、 巧みなステアリングワークによって、横方向に滑り出す。 迫るガードレール。当然、公から見れば自分に向かって来るように見える。 「うわあ!!」 悲鳴を上げる公。だが、スカイラインは何の危なげもなくコーナーをクリアし、さら に、その慣性を生かして、車体を振り子のように振る。 そして、そのまま、次の左コーナーを抜けていった。 『か、慣性ドリフトォ!?』 声も出せずに、公はそう思うだけだった。 そしてそれは聞こえてきた。 ”キンコン キンコン キンコン” 『な、なぜこんなところでキンコン鳴るう?』 (昔は付いてたんだよなあ。100キロ越えると鳴る変なのが・・・ ) (二重の意味で問題発言!) 公は思った。 『なんで失神できないんだあ!?』 (笑) 公にとっての恐怖の時間が続き(さすがに後半は慣れてきたが)、そろそろ帰ろう か? という事になった。 「よーし、最後の下りだ。気合い入れなくちゃね」 嬉々としてそう言った望に、公はひきつった笑いを浮かべながら思った。 『今まで気合い入ってなかったの? 清川さん?』 (笑) いくら慣れたと言っても、ダウンヒルはきつい。連続で襲いかかる横Gに公は耐えな がら、早くふもとについて欲しいと願うのだった。 (こういう時は長いんだよなあ、時間) だが、望の様子が変わった。チラチラ見やったバックミラーに二つのライトが映って いた。 「追いつかれた」 「え?」 望の声に公は振り返った。夜明け前の闇にライトだけがまぶしく光り、まるで望達の 乗るスカイラインに襲いかからんとするようだった。 「いつの間に?」 公の質問に、望は冷や汗を額に浮かべながら答えた。 「来るなと思っていたら、あっと言う間だったよ。速いよ、後ろ! 車種は何?」 「暗くて判らないよ。でもそんな大きな車じゃない。シビックかS13のシルビアぐら いだよ。 でもカエルだ。ヘッドライトがリトラクタブルだよ」 「まさかハチロクって言うんじゃないんでしょうね!?」 そう叫びつつ修正舵を取る望だったが、バックミラーから光が消えた事に気が付い た。 「え?」 望がそう言ったのと同時だった。 「うわわわわ!」 公が叫んだ。 後ろにいたはずの車が、するするとスカイラインの左横に並んだのである。 「ワンエイティ!!?」 そのホワイトボディを確認した時、公と望は同時に叫んだ。 その間にも次の左コーナーが迫ってきた。 「ブレーキいかれたの? オーバースピードよ!」 望はそう直感した。 だが、 「な、なんだあ!!」 またしても、公と望の声は同時だった。 どう見てもオーバースピードに見えた180SXは、イン側からスカイラインを抜き 去ったのである。 (いわゆるイン側からスコーーン!て言う状態だね) 「こんちくしょう!!」 かっとした望は言葉が悪くなってしまった。だが、公も目の前のあまりの状況に茫然 としてしまい、聞き取ってはいなかった。 望は必死で追いかけたが、その差は開く一方だった。 追いつけないと悟った望は、路肩にスカイラインを停めた。 「公くん、今の見た?」 「見た。なんであんなスピードでコーナーを曲がれたんだろう?」 「私が聞きたいよ。スピードの次元が違ったよ・・・ 」 二人は沈黙を続けた。だが、それも意味がないと気が付き望は言った。 「ともかく、帰ろう」 「うん」 帰る道中、二人は無言だった。 ただ、公は、その車のボディの文字に見覚えがあったので、その事を考えていた。 『確か、そう見えたんだよな・・・ 』 to be continue RZM-2「2」 第2回 「その名は甲斐秀一」 木枯らし吹く昼下がり、きらめき高校の駐車場に、一台の黒い4ドアセダンが走り込 んで来た。 駐車場内にしては速すぎるスピードだったのだが、突然、不自然な動きで、進行方向 に対して横に向き、白線で仕切られた駐車スペースにぴたりと止まった。 「? ? ?」 驚くというか、呆気に取られたと言うべきか、生徒や教師、職員等が呆気に取られて いると、その車のドアが開き、一人の男が降り立った。 「ふいーい。久しぶりだぜ。ここに来るのも」 そう言って、男はかけていたサングラスを外した。 身長は170cm台の半ば程か? 痩せ型の体系と顔つきは、知的な感じを与えると 同時に、鋭さをも感じさせていた。 年齢は20代半ばと言うところだろう。 男はサングラスを持っていたカバンに収めると、そこからメタルフレームのメガネを 取りだし、慣れた手つきでかけた。(伊達眼鏡か?) スーツではなく、赤と白のジャケットを着ていたため、かなり目立つ。 そんな彼を見た男子生徒の一人が声をあげた。 「甲斐センセイ?」 そんな声に彼は答えた。 「おお、久しぶり。みんな、元気にやってたか?」 すると男子生徒が数人集まり、口々に言い合った。 「やっぱり甲斐センセイだ!」 「戻ってきたんだ」 「くーー、これで少しは気が楽になるぜ!」 そんな会話を聞いていた”甲斐センセイ”と呼ばれた男は、頭をかきながら苦笑いを 浮かべた。 『レイのやつ、そうとう男子生徒の反発を買ってやがるなあ』 そんな事を思っていた彼の元に、彼の事を話していた男子生徒達が駆け寄ってきた。 「甲斐センセイ、帰って来たの?」 「ああ、一応な。まだ、正式な復職は3学期からなんだけどな」 「そんなあ。センセイがいなくなってから、伊集院を抑えられる人間がいなくって大変 だったんだよ。 俺ら男子生徒にとっちゃ、悪夢の日々だったんだから」 一人の男子生徒の愚痴るような口調に、”甲斐センセイ”は声をあげて笑った。 「情けないなあ。いいじゃないか、堂々と渡り合えば」 「そう言うけど、あいつを敵に回すって事は、女子の大半を敵に回すって事なんだから 気楽に言わないでよ」 「そうか? ほら、鈴鹿4時間耐久レースで活躍した主人 公、あいつなんか我が道を 行くって感じで、女子にも人気あるだろ? そう言う対抗の仕方だってあるんだぞ。少しは考えろ。 それに、あともうちょっとで卒業じゃないか。あと少しの我慢だよ」 「気楽に言ってくれちゃってさ」 男子生徒の声は、その言葉だけ取ると反発のようなものに受け取られるが、その口調 は敬愛や親しみと言ったものを含んでいた。 「そりゃ、甲斐センセイは弁護士だもんな。そう言う頭は働くだろうさ。 そういう事、休職するって時まで教えてくれないんだもんなあ」 やや不満を含ませたこちらの声に、”甲斐センセイ”は片手を上げた。 「いやあ、私立とは言え、弁護士の教師なんてのは珍しいそうだから、どうしても退い て見られそうだろ? 一人の人間、一人の教師、甲斐秀一として付き合って欲しかったんだ。 黙っていたことについては謝る。ごめんな」 こう素直に謝られると、何も言えなくなってしまう。 「まあ、そうかも知れないな。でも、俺達は甲斐センセイみたい先生、好きだぜ」 「そうそう」 口々に上がったそんな声に、その先生、甲斐は困ったような表情になった。 「ヤロー達に好かれてもあんまり嬉しくはないんだがなぁ」 そんな声に男子生徒達はニヤニヤと笑った。 甲斐はその苦笑いにつられたように笑いながら、一人の男子生徒に聞いた。 「ところで、その伊集院だが、今、どこにいるか知ってるか?」 「ああ、さっき、いつものように女子を引き連れて、中庭を歩いてたよ」 「そうか、サンキュ」 そう言って、甲斐は小走りに中庭の方に向かっていた。 その後ろ姿を見た男子生徒達は、小さくガッツポーズをするのだった。 「あら? 甲斐先生では、ありませんか?」 聞き覚えのある、のんびりした口調の声に、甲斐は振り返りながらその声の主の名を 呼んだ。 「ゆかりんか・・・ 」 だが、そう言いかけた甲斐だったが、その横に赤い髪の女子生徒の姿を認め、慌てて 言い直した。 「こ、古式か? 久しぶり。朝日奈も元気だったか? って相変わらずのようだな」 笑みを交えた軽い口調の甲斐の言葉に、その赤い髪の女子生徒、朝日奈夕子はやや口 を尖らせながら答えた。 「もう、秀ちゃんは久し振りに会ったってのにそれ? たく、もう、秀ちゃんがいなくなってからのこの一年、本っ当に堅苦しかったのよ。 帰って来てくれたのは嬉しいけど、もう卒業なんよ?」 そんな夕子に対して、甲斐は右手の人指し指で夕子を指しながら言った。 「よく言うよ。夏の4耐で、相当、やらかしたそうじゃないか? 噂は聞いているぞ」 「あれ? そうか、もう聞いちゃったのか? 驚かそうと思ってたのになあ」 残念そうに夕子がそう言うと、それを待っていたかのように、ゆかりが口を開いた。 「甲斐先生、何か、ご用事が、あったのでは?」 「おおっと、そうだった。またな二人とも・・・ 」 甲斐はそれだけ言うと、再び小走りでその場を離れていった。 甲斐の後ろ姿を見て、ゆかりは微笑みながら思った。 『甲斐お兄様、相変わらず、お元気のようですねぇ。安心いたしました』 (んんん? お兄様ぁ?) 伊集院レイ。この学校、きらめき高校の理事長の孫に当たり、伊集院財閥の御曹司と いう立場の男子生徒である。 彼のもとには、数人の女子生徒がいることが多く、この時もそうだった。 中庭で、レイは数人の女子生徒と会話を楽しんでいた。 「伊集院様、クリスマスパーティー、招待してくれますか?」 「あなたがそうお望みなら、手配いたします」 「あ、私も私も」 「はい、いいですよ」 そんな会話のさなか、ハスキーな男性の声が、レイの耳に届いた。 「よう、伊集院、相変わらずやってるな」 身体に電気が流れたようにビクッと身体を震わしたレイが、恐る恐るその声の方に顔 を向ける。 そこには木に片手を当てて立つ、甲斐がいた。 「か、甲斐先生。お戻りになったんですか?」 「あれ? 伊集院のじっ様から聞いてないのか? まあ、いいや。 また、ここに来る事になったんでな、よろしく頼むわ」 「は、はい。こちらこそ」 レイが普段とは全く違う、素直な口調で答えると、甲斐は腕を組みながら言った。 「ああ、今日、放課後空けておけよ。進路のことで話があるからな。 進路指導室まで来いよ」 「は、はい・・・ 」 一言の反論もなく、あっさりとうなずくレイに、まわりの女子生徒は、それぞれ同じ ようなことを考えていた。 『伊集院様は、どうして甲斐先生には頭が上がらないのかしら?』 と。 「きーよーかーわさん!」 望のクラスを訪ねた公は、明るい声で望を呼んだ。だが、それに対する望の声は相対 した暗く沈んだものになっていた。 「ああ、公くんか・・・ なに?」 「なにって、今週末、また、きらめき峠に走りにいくんでしょ? 俺もまた行きたいな って言ってたでしょ?」 「ああ、その事ね。 ・・・うん、いいわよ。一緒に行きましょう」 普段なら、望のその言葉は、明るく弾んだ物になっているはずなのだが、今日は違っ た。 暗い影がついたような、どんよりとした口調に、公はひきつった笑いを浮かべながら やや緊張したような声で言った。 「なんだよ、清川さん。まだ、ショックから立ち直れないの? 清川さんらしくないなあ。まだ、清川さん4輪に乗り始めて間がないんだから、他に 清川さんより速い人がいたって不思議はないじゃない。 いきなり速く走れるわけないんだから」 元気づけようとした公だったが、望の口調は元に戻らない。 「そうは思うんだけど、なんかレベルが違いすぎちゃってさ、 もう、茫然としちゃうんだよ・・・ 」 望が言っているのは、先週のきらめき峠での180SXの事だと言うことは、その場 に居合わせた公には判る。 その言葉の重さも判る公は、ゆっくりと言った。 「あのね。ひょっとしたら、あの180SXのドライバーと連絡が取れるかもしれない よ? なんなら再戦してみる? それとも話を聞いてみるという手もあるよ。それで参 考にすればもっと早くなれるさ」 公の意外な言葉には、望も無意識の内に立ち上がっていた。 「それ、ほんと? 公くん!?」 「いや、ひょっとしたら違うかもしれないけど、心当たりがあるんだ。 今日、連絡取ってみるよ」 「ホントに? お願い! もし連絡が取れたら私にも教えて。お願いね。公くん」 そう言いながら望は、これもまた無意識の内に公の両手を取っていた。 「あ」 「う、うん」 それに気がついた二人は顔を赤めながら、その手を離したのだった。 (純だなあぁ。・・・ほのぼの) その日の夕方、進路指導室を抜け出した(と言うより、進路指導室は建て前)、甲斐 とレイの二人は、きらめき峠の頂上付近、きらめき市街を見下ろすパーキングエリア で、黒の4ドア車から降り、冷たい風の中、車をはさんで会話をしていた。 「で、どうです? このプリメーラは?」 「おお、よく聞いてくれた。HP−10のオーテックバージョンだぞ。 悪いわけなかろうが」 「そうですね」 ----------------------------------------------------------------------------- 甲斐秀一所有 プリメーラTeオーテックバージョン(HP−10)データ ノーマルTeからの主な変更点 サスペンション、ショックアブソーバー、コンピューター変更 ABS エアバッグ カット等 エンジンSR20DE 150馬力(6400rpm)から180馬力(6800rpm)にチューン ナップ その他 ブレーキパッド交換(NISMO製) タワーバー 前(CUSCO製) 後(同上 特注品) ----------------------------------------------------------------------------- (な、なんじゃこりゃ・・・ ) 甲斐は胸のポケットから箱入りの煙草を取りだし、レイに見せた。 レイが片手で”どうぞ”という素振りを見せると、甲斐は一本を口に運んで火をつけ た。 「いやー、学校だとなかなか吸いにくいからな。これから、大変だよ」 「甲斐先生はヘビースモーカーですからね」 「言っとくがなあ。レイのお目付け役をやるようになってからだぞ。吸うようになった のは」 「わた・・・ 僕のせいだって言うんですか?」 「学校の人間がいない時は”私”でいいよ」 「私のせいだって言うんですか?」 やや、すねたようにレイが言うと、甲斐は笑いながら紫煙を吐き出した。 「大変なんだぜ、もうプレッシャーでさあ」 「嘘ばっかり。甲斐お兄様が、そんなやわな神経なもんですか」 「そうかぁ?」 「そうですよ。聞いていますよ、例の裁判。見事、逆転勝利だそうですね? 度胸がなければ、出来るものではないって言うことも聞いてます」 感心したようにレイが言うと、甲斐は照れくさそうに、人指し指と中指で煙草をはさ んだ左手で頭をかいた。 「まあ。あの裁判は、あの親子に対して、地主の嫌がらせみたいな面があったからな。 負けるわけには行かなかったのさ」 「甲斐お兄様らしいですね」 「本当は民事は嫌いなんだけどなあ。じっ様のおかげで民事ばっかりさ」 「それだけ信頼されてるって事ですよ」 再び煙草を口にくわえながら、甲斐は困ったような表情になった。 「俺に親父の様な能力を求められても、困るんだよな。じっ様はよく知ってるだろうが 俺は子供だったから、親父とお袋の事、あんまり覚えてないんだよな」 少し空気が湿ったような感じを覚え、レイはややためらうように言った。 「なら、私のブレーンになら、どうです?」 風が止まったわけでもないのに、二人の間の空気が固まった。 甲斐はくわえていた煙草を左手で取り、フィルターを親指で弾いて灰を落とした。 その後、ゆっくりと思い出すように口を開いた。 「聞いたよ。IMSPと言う名前はな」 「まだ、仮の名前の段階ですがね」 「 ・・・で、俺をどう使いたいんだ?」 甲斐の表情から感情という物が消え去った。それを見たレイも表情を引き締める。 「甲斐お兄様には、4輪部門のメインスタッフをしてもらいたいと思っています。 どうですか?」 レイの問い掛けに、甲斐はすぐには答えなかった。 「まあ、返事は今すぐでなくてもいいんだろ?」 「ええ」 「じゃあ、今日はここまでだ。 少なくとも卒業までは、教師と生徒。それでいいだろ?」 「はい」 レイがうなずくと、甲斐も納得したような表情になった。 「それじゃ、そろそろ帰るか。あんまり遅いと、じっ様がまた心配するからな」 甲斐はそう言って、運転席のドアを開けた。だが、レイが少しためらう素振りをした ため、甲斐は、ややからかうような口調で言った。 「なんだ? どうした?」 「 ・・・帰りは下りなんですから、来た時みたいに飛ばさないでくださいよ」 「心配するな。レイも乗せてるんだ。無茶はしないよ」 「絶っ対に約束ですよ」 「分かった分かった。軽く流すよ」 多少、困ったような表情で甲斐が運転席に乗り込むと、レイが助手席に座る。 「シートベルトはしとけよ」 「もちろんです」 そう答えたレイは、緊張というより、やや怒ったような表情になっていた。 「じゃ、行くぞ」 言うが早いか、甲斐はクラッチをミートさせ、プリメーラを発進させた。 「そんなに硬くなるなって、ゆっくりしたもんだろ?」 「え、ええ。確かにここまでは・・・ そうですね・・・ 」 レイの言う通り、プリメーラは駐車場の中まではどうと言うことは無かった。だが、 それもスカイラインに出るまでで、甲斐の操るプリメーラは、タイトなコーナーを滑ら かに駆け下っていった。 (滑らかにと言うと聞こえはいいんだが・・・ ) 「きゃーーーーーーーーーー!!」 「うるさいよ、レイ! 女みたいな悲鳴あげるなって」 「知ってるくせにいいーーーーー!!」 「おお、そうだったな」 「ああ、だから、嫌だって言ったのにいいぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃ!!!!!」 夕闇迫るきらめき峠に、レイの悲鳴が恨めしく響くのであった。 (合掌) to be continue RZM-2「3」 第3回 「藤崎とうふ店」 帰宅した公は、その足で隣の家に向かっていた。 公の家から見えるその家は、ごく普通の家なのだが、表通りに回り込むと、典型的な 個人商店になっていた。 決して派手さはないごく普通の個人商店で、その看板には”藤崎とうふ店”と書かれ てあった 「お、じ、さ、ん」 公は、そこにいた、やや年配の男性に話しかけた。 「おお、公くんか? 豆腐買っていくのかな? お使い?」 「え? ああ、今日は車を見に来たんです」 「車ぁ?」 その男性は中肉中背で、やや筋肉質な体つきだった。髪を短めに整え、不精髭などが 残っているが、それが不思議とだらしなくは見えない。 細めの目の男性は、間の抜けた声を出したが、やがて何事か思いついた様な表情に なった。 「そうか、公くんも18か。4輪の免許取るのか? そりゃ、興味あるよなぁ」 なぜか嬉しそうな表情を浮かべながらそう言ったその男性、名前は藤崎文也。 公の幼馴染み、藤崎詩織の父親である。 「まあ、そんなとこですね。いいですか?」 「おお、いいぜ。だけど、動かしちゃ駄目だぞ」 「判ってます」 実際の目的は、やや違うのだが、公はそのあたりを文也には曖昧にしたまま、すぐ横 のガレージに向かった。 公がガレージのシャッターを開けると、中から白い車体が現われた。 「やっぱり」 公は思わず独り言を言った。 その白い車体のドア、そこには素っ気ないゴシック体の文字で、 ”藤崎とうふ店”(”自家用”) と書かれていた。 それは紛れもなく、先週末きらめき峠で、公と望の乗ったスカイラインを抜き去って いった180SXであった。 「なにが、やっぱりなんだ? 公くん?」 公の後ろ、そこには、いつの間にか文也が立っていた。 「いやぁ、この車で豆腐を配達するのって、珍しいだろうなあって思うんですけど?」 「拓也が86持って行ってしまったからな。その時、FRでハッチバックと言ったらこ れ位しかなかったんだよ。 確かに、荷物は積みにくいけどな」 「はは、荷物の積み下ろしより、あくまでもFRにこだわるのか。おじさんらしいな」 苦笑いに近い笑顔でそう言った後、公は試すような口調で言った。 「おじさん、この前の日曜日の朝、きらめき峠で赤黒のスカイライン抜いて行ったでし ょ?」 「はあ?」 「ほら、インベタで苦しいラインなのに、スコーンって抜いて行ったでしょ?」 「そりゃぁ、また、一体どういう話だ?」 公は首をひねりながら、今度は本当に苦笑いを浮かべた。 「またまたぁ、おじさんたらとぼけちゃってぇ」 だが、不思議そうな表情を浮かべるだけの文也に、公の苦笑いが怪訝な物に変わる。 「おじさん?」 公の声に、文也が何事か思いついたように言った。 「おお、それか!? ・・・そりゃ、俺じゃないな」 「ええ? そ、そんなはずないでしょ?」 「いやぁ、違うって」 そう言った後、文也はたっぷりと間を置いてから、いたずらっぽい、そう、いたずら 小僧を思わせる笑みを浮かべながら静かに言った。 「そりゃ、詩織だ。 詩織がやったんだよ」 「ええーーーー!?」 (ええーーーー!?) きらめき高校の室内プールは温水プールなので、冬でも泳ぐことは可能である。 その日、望はそのプールで、みっちり練習をした後、帰宅の途についた。 そして校門の所で、一人の女子生徒に声をかけられた。 「清川さん、今、お帰りですか?」 「・・・ なんだ、如月さんか?」 望が振り返った先には、彼女と同じような髪の色をした眼鏡をした少女、未緒が立っ ていた。 「途中まで、一緒に帰りませんか?」 未緒がそう言うと、望はやや不思議そうな表情になったが、断る理由も見つからなか ったので、うなずきながら答えた。 「うん、いいわよ。一緒に帰ろ」 清川望と、如月未緒。この取り合わせは、一部の者から見れば意外なものと写ったか も知れないが、この二人は友情と言うか、一種奇妙とも言える、信頼と言うべきもので 結ばれていた。 この年の夏、鈴鹿4時間耐久レースに出場したきらめき高校自動車部、そのマネージ メントを担当したのが未緒だった。 それ以後、二人は急速に親しくなったのである。 「この時期まで部活ですか? 清川さんは、本当に泳ぐことが好きなんですね?」 その帰り道、未緒の言葉に、望は照れ笑いのような笑顔を浮かべながら答えた。 「ははは、ほら、私は試験もないし気楽なもんでしょ? 泳ぐぐらいしないと、気が抜けちゃって・・・ ね」 未緒は納得したような笑顔を浮かべながら、ゆっくりと2度ほどうなずいた。 「お父様のお仕事のお手伝い、つまり、キヨカワに務めながら、オリンピックを目指す というお話でしたね?」 「まあね。クラブに通いながらという事ね。 キヨカワは今度、4輪の方にも力を入れるという事になったから、どうしても、その お手伝い、という事になるのよね」 「実業団に行くばかりがオリンピックへの道、という訳でもありませんからね。 中学生でだって、クラブに行きながら金メダルを取った人だって、いるぐらいなんで すから」 未緒の言葉に、望は首を振りながら声もなく笑った。 「ま、オリンピックはともかく、泳ぐ事は好きだから、やめないよ。ずっと泳いでいく つもりだよ」 「そうですか・・・ 」 安心したような表情で未緒はうなずいた。だが、ふと、望の表情を見て、わずかなた めらいを経た後、未緒は聞いた。 「どうしたんですか? なんだか、浮かない顔をして。 清川さんらしくないですね?」 望は軽く首を振った後、照れたような笑いを浮かべながら、それに答えた。 「 ・・・私らしくないって言われてもなぁ。 そんなに落ち込んでるわけじゃないよ」 「やっぱり、普段とは違うんですね」 語るに落ちると言うべきか、望は自らの言葉でそれを肯定してしまっていた。 望は髪をくしゃくしゃとかき上げながら、降参と言った風な表情を浮かべた。 「参ったな、如月さんには。 確かにその通りだけど、なんで判っちゃうのかなぁ?」 「清川さんは、その時の心理状態がすぐに表情にでますからね。注意していれば判りま すよ」 「なんだか、それじゃぁ、私が単純みたいだけど、その通りだから反論できないな」 だが、望は不思議そうな表情になった。 「 ・・・でも、なんで如月さんは、そんなに私を気にかけてくれるの?」 未緒は不意をつかれたような表情になった。そして、やや、苦笑いの成分を含んだ笑 いを浮かべた。 「私は清川さんに、以前、悪い事しましたから・・・ 」 未緒の意外な言葉に、望は視線を空に向け、それがどういう意味か考えていたが、一 つ思い当たる事があった。 「 ・・・ひょっとして、8耐の時の事?」 未緒はゆっくりとうなずいた。 (そんな気にしないでもいいのに) 未緒の横顔を横目で見ながら、内心でそう思う望だった。 それは、この年の夏のことだった。 鈴鹿4時間耐久レースに出場した、きらめき高校自動車部(臨時の部でした)は、好 成績を残した。 その翌日、望は、公と二人きりで宿舎に残っていた。二人とも、前日のレースで心身 供、疲労しきったためで、他のメンバーは、鈴鹿8時間耐久レースを観戦していたのだ った。 その時(どさくさとも言うかも?)、望は以前から公に寄せていた想いを、打ち明け ようとした。 だが、その決意は空振りに終わってしまった。 鈴鹿8時間耐久レースを観戦していた未緒は、暑さのせいか倒れてしまい、宿舎に運 ばれて来たのである。 それは正に、望が公に想いを打ち明けようとしていた時だった。 その会話の前後は判らないとしても、その場の雰囲気でなんとなく判るもので、それ 以来、未緒はその事を気にしていたのである。 では、望はどうかというと、これがあっさりしたものだった。 残念だ、と言う気はしたが、”これはこれで良かったかな?”と思い、引きずるよう な事は無かった。 彼女は、以前、後輩に聞いた伝説に想いを込めて、卒業式の日、その思いを打ち明け ようと、気持ちを切り替えていたのである。 (清川さんらしいなあ・・・ ) 望をしては、未緒の恐縮ぶりに、かえって彼女の方が気を使ってしまうぐらいだっ た。 「私が考え込んでいたのはね。ちょっと前に、峠ですっぱりと抜かれた事があったの。 私もまだまだだなぁって、ちょっと落ち込んだんだ。でも、今はかなり立ち直った よ。 4輪は本格的に始めたばかりなんだから、これから、また頑張ればいいんだってね」 望の言葉に、未緒は、心なしか安心したような表情になった。 「そうなんですか。それを聞いて少し安心しました。 でも、清川さんが抜かれたなんて、驚きましたね」 「ああ、速い人なんて、いくらでもいるよ。それに、今も言った通り、私はまだ4輪は 始めたばかりだからね」 「誰なんです? その速いという人は?」 興味深げに聞いた未緒に、望は髪をかきながら、困ったような口調で答えた。 「それは、今、公くんにお願いしてるんだ」 「主人さんに?」 「う、うん。なんだか、思い当たるところがあるんだって」 そんな望の声に、未緒は、彼女には珍しい、悪戯っぽい笑みを浮かべた。 「な、なに?」 不思議そうな表情で望が聞くと、未緒はその笑みを浮かべたまま、それに答えた。 「清川さんも、打つべき手は打っているんだな、って感心していたんです」 望は頬を赤らめながら、慌てて答えた。 「ち、違うよ。そ、そんなんじゃないよ!」 だが、その表情からは説得力というものが、多少欠けていたのも、また、疑いようの ない事実だった。 「そんな、そんな事って・・・ 」 文也の意外な答えに、しばらく、茫然としていた公だったが、ようやくそれだけ言っ た。 文也は、さも面白そうな表情で、さらに続けた。 「その時間帯なら、そりゃ、詩織だよ。 きらめき峠のホテル群への豆腐の配達、免許取ったんで、今は詩織にやらせてるんだ よ。その時間帯なら、荷物を降ろして帰ってくる途中だろう。 少なくとも、俺じゃない」 「だって、詩織、トヨタがバイク作ってるなんてボケかましたんですよ!?」 慌てたように公は言ったのだが、文也は平然と答える。 「そりゃそうだろう。詩織にとっちゃ、車なんてのは、家の手伝いの道具にしかすぎな いからな。 どこが何を作っているか? なんてのは興味の対象外だろうさ」 そう言い終えた文也の表情は、先ほどまでの悪戯っぽいものだった。 「だけどなあ、公くん達が鈴鹿に行って、詩織もそれについて行ったんだが、それから 詩織も変わったよ。 それまではボンネットを開けた事さえなかったんだが、最近じゃ、点検なんかは、自 分でするようになったぞ。 公くんのおかげだな」 そう言って、文也は笑い声をあげたのだが、公にはそんな余裕は、全くと言っていい ほど無かった。 「だけど、清川さん、 ・・・俺のクラスメイトで、4耐のライダーなんですけど、その 清川さん、4輪は乗り始めて、まだ間も無いけど、それなりに速いと思うんです。 それを抜くなんて、いくらなんでも免許取ってから、半年かそこらでしょ? どうし て、そんな技術があるんです? 詩織に?」 もはや、必死とも言える口調になった公の質問に、文也は悠然と、何かを思い出すよ うな口調で答えた。 「今もそうかもしれないが、詩織は意外とスピード狂だろ?」 「? ・・・あ、そう言われてみれば」 公は幼い頃、詩織と文也の車に乗った時の事を思い出した。 峠の道で公は、かなり怖い思いをした事があったのだが、その時、詩織は、 「ジェットコースターみたいで面白い!」 と喜んでいたものだった。 そのジェットコースターと言えば、詩織は遊園地の乗り物の中で、ジェットコースタ ーは好きなものの一つだった。 公がそんな事を思っていると、文也は嬉しそうな笑顔を浮かべながら、さらに続け た。 「さすが俺の娘と言うべきか、詩織のスピード感覚は、なかなかのものがあるみたい だ。 昔から、俺や拓也のナビに座っても、全然、平気だったからな。 それに免許を取ったのは半年前だが、・・・ ?」 そこまで言って、文也はばつの悪そうな顔になった。 「まあ、こっから先は、あんまり、おおっぴらには出来ない話だな」 苦笑いを浮かべながら、公にウインクした文也の表情から、公はそれが何を意味する ものかが理解できた。 (出来てしまった。かな?) 「お、おじさぁん・・・ 」 そう言ったきり、公は絶句してしまったのだが、文也は逆に、面白そうな表情になっ て続けた。 「朝早い峠なんて、誰も走ってないから、そこら辺りは、まあ、いいだろ?」 (良くねえよ!) 半ば、茫然としたままの公に、たたみかけるように文也は続けた。 「親の俺が言うのもなんだが、詩織は頭がいいからな。俺が教えた事、あっと言う間に 自分の物にしちまうから、あっと言う間に速くなるぞ」 嬉しそうな、自慢しているような表情の文也に、公は半分、独り言のように言った。 「でも、詩織、そんな事、一言も、言わなかった・・・ 」 それを聞いた文也も、公と同じような口調で答えた。 「あいつは真面目だからなあ。そういう事は言い出せなかったんじゃないのかな? 家の手伝いとは言え、アルバイトになるんだからな・・・ 」 公はその声を耳にはしていたが、どうしても納得できなかった。信じられなかった。 詩織に自分の知っている意外に、そんな一面があったことを・・・ 。 「るんたった、るんたった」 意味不明な独り言(と言うか独り歌?)を口ずさみながら、館林見晴は下校しようと きらめき高校内の廊下を、スキップしながら校門の方向に向かっていた。 「お待ちなさい」 そんな彼女を呼び止める声がした。 その声に聞き覚えがある見晴は、恐る恐る振り返った。 「ひ、紐緒さん」 振り返った視線の先、そこには白衣を着た女子生徒が立っていた。 紐緒結奈である。 「間に合ったようね。用があるから科学教室に来なさい」 「え、でもぉ。私、今から大通りのケーキ屋さんに行くんですう」 無駄だとは知りつつ、断ってみた。だが、やはり結奈には通じない。 「後日にしなさい。 今から実験をするの。その手伝いをしなさい」 「ええーー。やっぱりそれですかぁ?」 「主人くんの情報を教えてあげるから。と言っても?」 「はーい!」 うってかわった見晴の返事に、結奈は内心で肩を落とす。 『扱いやすい娘ねぇ。あんなにいい実験結果を出すのだから、それはそれでありがたい のだけれど』 そんな事を思いながら結奈が歩いてく後ろを、見晴は続いていった。 その後、科学教室の方面からかん高い排気音が轟くのだった。 (あ、でもこの話、あんまり本編とは関係ありません)(おいおい) to be continue RZM-2「4」 第4回 「交差する思惑」 「おはよう、お父さん」 年の瀬も迫る、身を切られるような冷え込みの冬の朝。詩織はいつものように自分の 部屋から作業場のある一階に降りて来た。 外はまだ暗く、冬ということもあり、朝というより夜と言うべき雰囲気である。 そこには、180SXに荷物を積もうとガレージに向かう、父親の文也がいた。 「おお、おはよう詩織。今日も寒いな。 もう少し待ってろ。今、積むからな」 「うん」 文也に続いてガレージに入った詩織は、シャッターを開けた後、そう言って運転席に 座り、シートやミラーを調節して、180SXのエンジンに火を灯した。 「よし、っと」 荷物を積み終えた文也がハッチバックのドアを閉める。 「今日は一段と路面温度が低いからな。足に注意しろよ」 「はい」 詩織はそう答えると、静かに180SXを発進させていった。 後に残った文也はそのテールランプを見送りながら、自分にしか聞こえない声で言っ た。 「まったく、詩織はいい娘だな。俺の娘とは思えん、拓也とはえらい違いだな」 だが、その言葉とは裏腹に内心では、 『それでも、内に秘めている闘争心のようなものも、あるにはあるはずなんだがなあ』 とも思っていた。 (うーーん、父親ならではのご意見ですね) その頃きらめき峠では、一台の自動車が、上り、下りにと峠道を攻めたてていた。 インプレッサWRXである。 鮮やかなブルーのその車体は、軽やかにコーナーを駆け抜けていく。 ひとしきり走り終えたインプレッサは、頂上付近のパーキングエリアにその車体を停 めた。 そして、運転席と助手席から二人の男が降り立った。 一人は20代後半、もう一人は40才前後というところだろうか。若い方の男が近く にあった自動販売機でコーヒーを2本買い、年配の男に一本を手渡す。 「あっちっち」 若い男がそんな事を言い、コーヒーのタブを開ける。インプレッサに寄りかかりなが ら、二人はコーヒー缶に口をつけた。 そして、白い息を吐き、若い男がつぶやくように言った。 「松原さん、俺達こんな事していていいんですかね?」 松原と呼ばれたその年配の男は、若い男に見向きもせずに答える。 「嫌なのか? 井上は」 「いや、こう言うのは好きですし、これで給料もらえるんなら文句はないんですが」 「なら、いいじゃないか」 「でも・・・ 」 井上と言う名の若い男が、困惑気味な表情を浮かべる。松原は視線をそのままに、 ぼそりと言った。 「監督なら、しばらく何も言わないさ。そう言う仕掛けになってるんだ」 「それがわかんないんです!」 多少いきりたったように、険しい顔で井上が言った。 「大体、なんで監督があんな奴にぺこぺこしてるんです? あの、甲斐って何者ですか?」 松原は淡々とした口調でそれに答える。 「カマイタチの甲斐って言ってな。本家でも有名なワルだよ」 「そんな切れ者が、なんで高校の先生なんてやってるんです?」 皮肉めいた井上の声に、松原はすぐには答えない。缶コーヒーを飲み干し、一息つい てからゆっくりとした口調で言った。 「だからさあ、切れすぎたんだよ」 「?」 釈然としないといった表情の井上に構わず、松原は助手席に乗り込んだ。 「さて。夜が明けきらないうちに、もう一走りするか。 まだここに、慣れてないだろ?」 「あ、は、はい」 井上もそれに答え、運転席に乗り込んだ。 (なんか、このシーンて・・・ ) 峠を駆け下るインプレッサの運転席で、井上はバックミラーに光を認めた。 「どうやら、地元の走り屋とご対面のようです。 やりますか?」 「そりゃ、こんな車に乗ってこんな時間に走っていれば、意思は通じるだろ? ま、今の若いもんがどう考えているかは知らんがな」 「じゃあ、やります」 「あまり無茶はするなよ。軽く流していけ」 「はい」 そう言ったかと思うと、井上の表情が変わった。アクセルを踏み込み、インプレッサ の挙動が変わる。 そのインプレッサの背後に、白い車体が近づいた。 180SXだった。 「速いですね。なかなかやりますよ。後ろ」 「喋るな。そろそろ、そんな余裕ないだろ?」 「はい!」 その通りだった。井上という男のドライビングテクニックは、相当なものだったのだ が、180SXを振り切ることは出来なかった。 そして、インプレッサのインがわずかに開いたかと思ったその瞬間、180SXがそ こに飛び込んだ。 「なに!!」 松原と井上の二人は同時に叫んだ。 二人の目には180SXは完全にオーバースピードに見えたのだが、妙な動きを見せ ながらインベタでコーナーをクリアし、インプレッサを抜き去ってしまったのだから。 (また、これです) 井上は必死で後ろに付こうとしたのだが、速度の差は明白であった。 「もういい、そこの路肩に停めろ」 潮時を感じて言った松原の声に、井上も素直にそれに従う。 「 ・・・あれは、マンガの世界だけだと思ってました」 長い沈黙の後、井上が言った。 「いやあ、あれをやれるサーキットが、実際にどこかにあったぞ」 松原の声に、井上は意外そうな表情でその声の主を見た。 「松原さん、知ってるんですか?」 「ああ、一応な。 水はけ用の側溝にタイヤを落として、そこにひっかけるようにして曲がるんだろ? ま、実際に見たのは、俺も初めてだがな」 驚いたというより、感心した、いや、むしろ呆れたかのように松原が言うと、それき り二人は再び黙り込んだ。 そして、いつの間にか東の空が白みだした頃、松原が言った。 「なるほど、こいつは確かに面白い話だな」 「そうですね」 井上はそう答え、静かにインプレッサを発進させた。 「まいったなあ」 2学期もあと二日を残すのみとなった日の朝、学校に向かいながら公は悩んでいた。 望に頼まれ、180SXのドライバーを捜していたのだが、それが、あのような結果 を見るとは思っても見なかった。 詩織の父親が運転していると思い込んでいたので、それを望に話すべきかどうかの判 断がつきかね、数日が過ぎてしまっていた。 さらにおかしなもので、学校の内外、車に興味がある者の間で噂に上っていたのであ る。 「夜明け前の180SX」という存在として。 もちろん、以前からそう言った噂はあったのだろうが、それが耳に入ったのが、つい 最近となってしまったのである。 この事を望に話して良いものかどうか、公は悩んでいた。 ともかく、詩織に直接聞こうと思っていたのだが、なかなかその機会に恵まれなかっ たのだ。 「おはよう、公くん」 そんな声に公は振り向いた。 「ああ、清川さん。 ・・・おはよう」 公を呼び止めたのは望だった。 「どうしたのよ。そんな暗い表情しちゃって? 公くんらしくないなあ」 心なしかどんよりとした公の目を見て、明るい笑顔を浮かべた望が聞いた。 「う、うん。別になんでもないよ」 公はそう答えたものの、望の言う通りだろうなと自分でも判った。 「あのさ、清川さん」 「ん? なあに?」 「例の180SXの話だけどね」 「うん。どうなったの?」 「あ、うん。もうちょっと待ってて。少し確認したいことがあるから・・・ 」 「?」 多少、歯切れの悪い公のセリフに、望は不思議な思いにとらわれながらも、素直に公 の提案を受け入れた。 「うん、公くんがそう言うんなら・・・ 」 「冬休み中にはなんとかなると思うから」 「 ・・・うん、待ってるよ」 望はそう答えた。 公がそう言うのならと望は納得したのだが、冬休みが明けることを待たずして、新た な進展を見せるのだが、この時の二人が知る由もない。 「あの二人がねえ・・・ 」 そんな二人を校舎の3階の一室から見ていた甲斐が、その後ろに立っていた伊集院レ イに言った。 「意外ですか?」 なぜか嬉しそうなレイの声に答えるかの様に、甲斐も嬉しそうな口調で言った。 「いやあ、自動車部とは、ずいぶん面白そうなことをしたじゃないか? と思ってな」 「監督は京間さんですよ」 「そうだってな。俺はグンからは聞いてないけど。 やや皮肉めいた甲斐の答えに、レイは多少困ったような表情でそれに答えた。 「連絡がつかなかったんですよ、きっと。 あのころは甲斐お兄様忙しかったから・・・ 。 僕もあの京間先生と、先生が知り合いだなんて知りませんでしたよ」 「そうだよな。大学以来だからな。 俺だってグンが先生だなんて、笑っちゃうぐらい 想像できなかったよ」 笑いながら甲斐はそう言ったが、やがて表情を引き締める。 「それにしても清川さんはともかく、主人がねえ。 俺が知ってる主人はそんなに目立たない生徒だと思っていたんだが、いつの間にあん なになったんだ?」 レイは苦笑いを受けべながら、甲斐の知らない、きらめき高校の時間の空白を埋める かのように答える。 「公くん、甲斐お兄様がいない間に、急成長したんですよ」 「ほう、公くんねえ・・・ 」 レイの答えから、ややポイントの外れた返事を甲斐がする。その意味に気づいたレイ は、なぜか、頬を染めながら言った。 「い、いいじゃないですか。そんな事」 「ははは」 ひとしきり笑い、甲斐が再び表情を引き締める。 「だけど、知ってるのかね? あの二人が・・・ 」 そう言いながら、甲斐は一枚のレポート用紙に目を通す。 「でも、手掛かりは多い方がいいんじゃないんですか?」 「 ・・・まあな。まあ、放課後にでも聞いてみるわ。駄目元でな」 甲斐はそう言って苦笑いに近い笑みを浮かべた。 「それにしても、いきなりのヒットだからなあ。 まさか在任中に事を起こすとは思わ なかったな」 そんな甲斐の言葉に、レイが反応した。 「あのお話、受けてくれるんですね?」 「ああ、悪い話ではないからな。 ・・・むしろ好きだし・・・ 」 照れたような口調の甲斐の答えは、レイを満足そうな表情に変えた。それを見た甲斐 は、少しくだけた口調に変わる 「しかし、なんか仕事ないのか? 放課後まで長いぞ」 甲斐は今のところ、非常勤講師という身分である。 2学期の終りのこの時期に、学校に戻ったとしてもカリキュラムに入る余地はない。 レイが入学した当時はレイのクラス担任にもなっていたのだが、今は、”無位無官” の身である。 結局、学校に出ては来るものの、その一日は、「よく言って、給料泥棒」と自ら評す ものだった。 「お爺さまは、甲斐お兄様に私のお目付け役をさせたいんですよ。 のんびりしていて くださいな。 私が卒業するまでは、・・・ね」 悪戯っぽい笑顔でそう言ったレイに、甲斐も照れたように笑った。 「まあ、そうしようか・・・ 」 レイの言葉の言外に、”自分が卒業したら、存分に働いてもらいますからね”と言っ ているような気がした甲斐だった。 不思議なもので、この数日、公と詩織はじっくりと会話をする機会に恵まれていなか った。 試験があったり様々な雑用があったりで、お隣に住み同じクラスでいながら、なかな か時間が取れなかったのである。 公としては、詩織に話を聞きたかったのだが、それもならず、やや、フラストレーシ ョンがたまる日々だった。 実際のところ、夏の鈴鹿4時間耐久レース以来、詩織と公は「疎遠」とはとても言え ないが、それでもそれまでとは明らかに違う雰囲気になっていた。 校内での公の人気は、それまでも相当なものだったが、鈴鹿4時間耐久レース以来、 そのボルテージはさらに上がった。 ただ同時に、そのパートナーとなった望と噂になってしまうのも、ある意味無理のな いことだった。 詩織にはそれがなんとなく引っかかってしまい、それ以来、わずかではあるが二人の 距離が離れてしまったのである しかし、公にしてみれば、それほどそれを感じてはいなかった。 (相変わらずと言えば相変わらず) そのせいか、この日も公は詩織に話を聞こうとしたのだが、やはりそれはならなかっ た。 「なんでかなあ」 放課後、(と言っても、午前中で終りなのだが・・・ )中庭で公はポツリと独り言を言 った。 「公くん、どうしたの? そんなにたそがれちゃって?」 「ああ、清川さん」 その声の主を認めた公は、首を振りながら答えを続けた。 「う、うん。ちょっと上手くいかない事があって、悩んでるんだ」 歯切れの悪い公の返事に、望は不思議そうな表情を浮かべたが、やがて公を元気づけ ようとするかのように明るい口調で言った。 「なんだよ、公くんらしくないなあ。もっと元気出していこうよ」 「 ・・・うん。そうだね」 公はそう答えたものの、その口調は、その言葉の意味から対極にいるものになってい た。 『一体、どうしたって言うのよ、公くんは?』 そんな事を考えていると、二人に声をかける者が現われた。 「おい、主人。それに清川さん」 「甲斐先生?」 公と望は同時に声を上げた。 二人の背後に、甲斐が立っていた。 「どうしたんですか? 甲斐先生?」 公の問い掛けに甲斐はうなずきながら答えた。 「まあ、色々と聞きたい事があってな。 ・・・と、その前に元気でやってたか?」 「は? ・・・ええ、まあ」 そんな質問をする甲斐の真意を計りきれず、公は間の抜けた返事をした。 公が一年の時のクラス担任が、他ならぬ甲斐であった。 2年生の秋、”ちょっとした事情”で学校を離れたのだが、さっぱりとした性格や、 ひいきなどしない公平な態度などから、公は甲斐を尊敬していた。もっとも、それは公 だけではなかったのだが・・・ 。 なにしろ、その当時は公自身でさえ、自分は人の印象に残るような生徒ではないと自 覚していたのである。 それだけに、甲斐が自分にそんな風に言う事に、違和感を覚えた。 その違和感は次の甲斐の質問である程度、解消されることとなる。 「聞いたよ。鈴鹿4時間耐久レースでのこと」 「 ・・・ああ、それでですか・・・ 」 納得したような公の表情と口調に、甲斐は多少疑問を憶えたものの、さらに続けた。 「まあ、それだけではないんだけどな。実際、公はそれ以外でも頑張ってるようだし、 俺も驚いてるんだ」 「で、なんですか?」 替わって聞いた望の問に、甲斐は本題を思い出したように言った。 「ああ、そうそう。 二人は車関係には詳しそうだから、一つ聞きたいことがあってな・・・ 」 甲斐はそう言って二人に何事か聞いた。 しばしの時間が流れた後、公が驚いたような声を上げた。 「白い180SXううぅっ!!!!!」 to be continue RZM-2「5」 第5回 「挑戦?」 甲斐から意外な質問をされ、公はほとんど無意識の内に聞き返していた。 「ワ、180SXがどうしたんです?」 明らかに動揺した公の声に意外な思いがした甲斐は、それまでしていた、ややくだ けた表情を引き締めた。 「なんだ? 何か知っているのか?」 その質問に答えたのは、その対象となっていた公ではなく、一緒に聞いていた望だっ た。 「ワンエイティって、きらめき峠の夜明け前に現われるって言うワンエイティの事でし ょ?」 「ああ、そうだけど、知ってるの? 清川さん」 甲斐の問いかけに、望は心なしかひきつった表情の公に視線を向けて答えた。 「なんでも公くんは心当たりがあるらしいのよ。 私には教えてはくれないんだけど・・・ 」 首をすくめる望に対して、表情を引き締めたまま、甲斐はその視線を公に向ける。 「本当か? 主人?」 「いや、あの、心当たりと言うか、おぼろげながらと言うか・・・ 」 歯切れの悪い公の答えに、甲斐は公を正面に見据え問いただした。 「それでもいい! 主人、知っていることがあったら、なんでもいいから、教えてく れ!」 自分の知っている雰囲気とはあまりにも違う甲斐に戸惑いながらも、公は聞いた。 「そもそも、なんで甲斐先生が、その180SXとどうつながるんです? 全然話が見えないんですけど・・・ 」 そんな公の言葉に、甲斐は我にかえったように口調を整える。 「あ、ああ、そうだな、確かにそう思うよ。主人から話を聞こうと思うんなら、詳しい 訳を話さなきゃならんだろうな」 甲斐は一つ咳払いをした後、公の質問に答えた。 「結論から言うと、その180SXと勝負したいということなんだ」 「え? 先生と!?」 驚いたように公が聞き返すと、甲斐は苦笑いを浮かべる。 「話は最後まで聞け。相手は俺じゃないよ」 「誰なの?」 興味津々と心配と言う成分の双方を、半々に含ませた表情の望が聞いた。 「本年度の全日本ラリー選手権2位の井上隆。清川さんなら知ってるかな?」 「あ、4輪の方はあんまり・・・ 」 少し困ったように望が言うと、”しょうがないかな”という表情で甲斐は続けた。 「そういう事なら仕方がないな。まあ、それは置いておくとして、どうだ、主人? 走り屋なら、不足のない相手だと思うが?」 「ちょ、ちょっと待ってください。 そんな事言われたって、何の事だか、まだ全然判 りませんよ。一体どう言うことです?」 「あ? ああ、そうか。自分で最後まで聞けって言っておいてそれはないな。順序立て ないとな・・・ 」 甲斐は頭の中でしばらく思考を巡らしてから、ゆっくりとした口調で続けた。 「IMSPと言うのがあるんだ」 「IMSP?」 公と望の声がそろった。 二人の声に、平静な口調で甲斐が答える。 「まだ、正式な組織になっているわけじゃないし、まだ仮名の段階なんだが、一応、来 年の4月辺りから活動を始める予定になっている。 伊集院モータースポーツプロジェクト。略してIMSP。名前で大体概要はつかめる だろ?」 「いやあ、なんとなくは判りますけど、具体的な事は、全然・・・ 」 半分困ったような表情で公が答えると、望が続いた。 「モータースポーツの底辺を広げようって言う、よく聞くアレでしょ?」 「まあ、大筋じゃ間違ってはいないな。 なにせ日本ってのは車の生産高じゃ世界有数だが、その使い方となるとお粗末とは言 わないものの、優秀とはとても言えない」 公は納得したように、望はやや不満な表情で、同時にうなずいた。 「だけど実際には、車やバイクをスポーツ用具として使おうとしても使う場所がない。 と言うか、野球やサッカーのように気軽に接する機会が少ないし、また、それに対す る理解もまだまだだ。 そこで、ジムカーナやカートの出来る施設や、公道を閉鎖してのタイムトライアルや ラリー。その他にもドライビングスクールや、安全運転教室エトセトラを通して、運転 するだけでなく、見るという事を通して、モータースポーツの対する理解を、老若男女 を問わず広げていこうと言うわけだ」 自信に満ちた表情で甲斐がそう言うと、公は感心したような表情になったが、望はや や懐疑的な視線を甲斐に向けた。 「うーーん。そりゃ、理屈は分かるし、そう言うのってとっても大切だと思うけど、だ けど、そう言うのって採算が取れにくいから、長続きしないんだよね。 結局、利益優先だから・・・ 」 むしろ苦味の成分を含んだ表情で言った望に対し、甲斐は胸を張って答える。 「大丈夫だよ。清川さんの心配はもっともだが、今回はそれには及ばない。 なぜなら、このプロジェクトで元を取ることは考えていないんだ」 「はあ?」 甲斐の答えに、公と望はほとんど同時に間の抜けた声を上げてしまった。そんな二人 の反応に対し、甲斐はなぜか嬉しそうな表情になって続けた。 「たとえば、日本でWRCラリーを開催しようとしたって、そうはいかないだろ? ま、いろいろ理由はあるんだろうが、そもそも、今の日本じゃ、コース設定そのもの も難しいからな」 「そりゃそうですよ」 さも当然と言った表情で公が言った。 「公道を使ってのレースなんて、日本じゃ出来る訳ありませんよ」 「なんでだ?」 「なんでって・・・ 、ラリーは公道を”借りて”やる形なんでしょ? そりゃ無理とは言 わないけど、実際には難しいですよ」 「ラリーと言うのは意外と思うかもしれないが、交通法規や法定速度を守って行われた りするもので、めちゃくちゃスピードを出すものでもない。 そもそも、一般車と混じりながら競技が行われているんだよ。 スピードを出して争うのは、主にSS区間だけだよ。SS区間を人里離れた地域に設 定すれば不可能ではないだろ? それに大都市だって、シーズンともなれば、マラソンだ。駅伝だって閉鎖されちゃう じゃないか」 一言えば、十返ってくると言った感じの甲斐に戸惑いながらも、なぜだか公はむきに なって反論した。 「そうは言いますけど、マラソンや駅伝で交通事故なんかは起こりにくいでしょう!? ラリーとなれば事故だって起こりかねない。そう、民家に突っ込んだりしたら、問題 になっちゃいますよ」 公の問い掛けに、まるでその答えを用意してあったかのように甲斐は平然と答える。 「どこだったか関西に、猛烈なスピードで屋台を引き回すお祭りがあったよな? 狭い路地なんかをでかい図体の屋台を引き回すんだ。通りの民家に突っ込んだり、電 信柱倒したり、けが人がでたり、それに混じってケンカがおきたり、そりゃもう大騒ぎ だ。 だけど、祭りをやめようという話にはならない。なぜかな?」 甲斐の言葉は質問の形を取ってはいたが、それはある意味、結論を言っているという 事でもあった。 その意味が判る公は、次の言葉を継げなくなり、端で聞くだけだった望も、口にこそ しないが、その意味が判っているとことは表情が物語っていた。 二人の雰囲気を読み取った甲斐が、ゆっくりと続けた。 「そうなんだよ。要は一般的な理解と歴史の差、なんだよ・・・ 。 バイクを見れば暴走族。四輪をちょっといじれば暴走族。そんな偏見がはびこる世の 中だが、ある意味それも仕方がない。 暴走行為とは名ばかりで、ただただ暴れたい、なんてやつらは問題外だが、人に迷惑 はかけないと言って、公道でレースまがいのことをするのはやはり問題だ。どんなに理 屈を並び立てても違法は違法なんだ」 キッパリと言いきった甲斐に望が何か言い返そうとしたが、構わずに甲斐は続けた。 「だが、その気持ちは判らないでもない。日本で自動車競技をしようとしたら、費用が べらぼうにかかる。 車両自体にもかかるし、改造費や燃料代、移動費やら、なんでも かんでも、のべつ幕なし金がかかる。 さらにその競技施設自体の数が少ない。施設を作りたくても、騒音やら環境やらで作 るに作れず、道路を借りるに借りれない。 よって彼等は公道に流れ、さらに悪印象を与えてしまい、理解が進まず、施設建設な どは困難が増すばかり、金はさらにかかり、 ・・・悪循環だな・・・ 」 最後はため息交じりになっていた。 その時、沈黙していた望が口を開いた。 「その悪循環を断ち切ろうというわけ? そのIMSPが?」 「そうだ。決して今すぐにという訳じゃない。ゆっくりと、だが確実にモータースポー ツに関しての理解を広めていくというコンセプトなんだ」 「 ・・・でも、わかりません」 これは公の質問だった。 「そんな手間暇かける理由はなんです? それで世界に通用するライダーやドライバーを生み出そうって言うんですか? 確かにそれは面白い話です。だけど、いくら採算は度外視と言ったって、それじゃ元 が取れないことおびただしいじゃないですか!?」 ほとんど叫び声に近い公の声だったが、甲斐はそれ自体にはあまり関心を示さなかっ た。甲斐が関心を示したのはその内容だった。彼は感心したような表情で公の質問に答 えた。 「なかなか鋭い意見だ。学年一位は伊達じゃないな。 確かに優れたドライバーやライダーを育てるというのもある。だが、主人は一つ見落 としているぞ」 「?」 「スポーツ云々の前に、車というのは道具だ。そしてそれを作るということは産業だ。 この意味分かるか?」 「ああ!」 「?」 公にはその意味がおぼろげながら理解できた。(”?”は清川さんです) 「モータースポーツを理解するということは、間接的に、四輪二輪双方の自動車産業に 対する理解が深まることになるわけだ。 それは自動車という商品に対する”目”が高くなるという事を示している。そしてそ れは、日本車という商品の国際的な商品力を高めるということにもつながる。 安くて丈夫だが無個性、なんて言う問題点は、ユーザーがシビアで正確な目を常に向 けていれば、おのずと解決されるものだ。 さらに、自動車そのものに対する安全認識。交通環境に対する問題点の指摘、それに 伴う道路交通システムそのものに関するインフラ整備などを考えていけば、その経済効 果は計算できない。少なくとも国家予算の比じゃないね」 そう言った甲斐の表情は、公や望が何度も見たことのある悪戯っぽいものになってい た。 公と望は、一気にまくし立てられた、あまりにもスケールの大きな話の内容に、しば らくの間、茫然とするだけだった。 公はようやくの事で自分を取り戻し、甲斐に聞き返した。 「いや、あの、お話はなんとなくですが分かります。ですけど、それでなんで、し・・・・ ・・180SXとつながるんですか?」 公の質問に、甲斐は困ったような、それでいて嬉しそうな笑い顔を浮かべながら答え た。 「ま、名目上はそのプロジェクトのための人材発掘と言うことなんだが、実際は単なる リターンマッチだよ。 その相手となる井上を、数日前、きらめき峠で180SXはあっさりと抜き去ったん だ。 井上ってのは、これがまた結構負けず嫌いでな。 そうとう切れてしまったそう なんだ」 ”しょうがねえなあ”と言った風の笑いになった甲斐が、さらに続ける。 「まあ、なんにしろ、井上を抜いたんなら相当な腕であるには違いない。 ちょっとばかり興味があるんだな」 「で、勝負してどうするんです?」 それまで黙って聞いていた公だったが、ぽつりと言った。 「ん? うん、そうだな。どんな人間か確認した上で、本人にその気があれば、まあ、 スカウトと言うことになるだろうな。 もっとも、もうすでに他のチームか何かにいる可能性はあるがな」 「それはないと思いますが・・・・・・」 歯切れ悪く公がそう言うと、甲斐が不思議そうな顔で聞いた。 「なんだ主人、さっきからなんか意味有りげだなあ。 どういうことだ?」 「いや、どうということはないんですけど、多分、その180SXの人、そう言った方 面には進まないと思いますよ」 「なんでだ?」 「直接聞いたわけじゃないけど、本人はそんなに車が好きって訳じゃないみたいだか ら・・・ 」 「そんな馬鹿なことあるか!?」 ほとんど反射的に甲斐がそう言った。 「全日本ラリーで優勝争いをするぐらいのドライバーを、地の利があると言ったって、 あっさりと抜くような奴が車が嫌いなわけないだろう?」 「公くん、甲斐先生に教えたくないの? そのドライバーのこと」 甲斐に続いて、今度は望が公に聞いた。その瞳は彼女にしては珍しく猜疑心を伴った ものとなっていた。 「え? そう言うわけじゃないけど・・・ 」 「確かに、公道でのレースなんて危険だから、あんまりいい事じゃないけど、私、興味 あるんだけどな・・・ 」 「清川さん・・・ 」 公は しばらくためらう素振りを見せた後、甲斐に向かって言った。 「分かりました。とにかく1度当たってみます。ですけど、あんまり期待はしないで下 さいよ」 「いや、それでもいいよ。とにかく任せるからな」 甲斐はほっとした表情で公の肩を叩きながらそう言った。それを受け、公も無言でう なずいた。 そんな時、望が聞いた。 「でも、どうして甲斐先生が、その ・・・IMSP、とかに関係してるの?」 望の疑問は彼女にしてみればごく当然のものだったが、甲斐にとっては意表をついた ものらしく、意外そうな表情を浮かべた。望はさらに続ける。 「前から聞こうとは思っていたのよ。 これは私だけじゃなくて、そう思っている人多いと思うけど、伊集院くん、どうも甲 斐先生が苦手みたいなんだよね。 そりゃ、誰にだって苦手な人はいるだろうけど、あの伊集院くんが、と言うのがどう も信じられないんだよ。 どうなってるの?」 彼女に似つかわしいストレートな言い方の質問に、甲斐は苦笑いを浮かべた。 「まあ、はっきり言えば、いろいろ事情というのがあるんだよ。今、詳しくは言えない んだが、そういう事だと思ってくれや」 「ふーーん」 望と公の声が重なった。 二人ともそんな答えでは完全には納得出来なかったが、それ以上聞くことはしなかっ た。 望は頭の後ろで手を組んで、他人事のように言った。 「しかし、スカウトか。モータースポーツでもそう言うのがあるんだなあ」 「何言ってるの。清川さんも候補の一人だよ」 「え?」 「清川さんは水泳もやっているから、オリンピックとの兼ね合いもあって表沙汰にはな っていないんだが、夏には2輪部門でリストアップされていたそうだ」 「夏? ああ、4耐か・・・ 」 望はこの夏の鈴鹿4時間耐久レースの事を思い出した。さすがに今は落ち着いたが、 あの頃はささやかではあるが、マスコミなどにも追いかけられたものである。 自分の知らない意外な事が進んでいると知って、望は困ったような表情になり、言葉 を無くしてしまった。 「それじゃ、俺、行きますから」 ほんのわずかな時間の沈黙を公が破った。 「あ? ああ、頼むな、主人」 突然の公の言葉に、少し間が空いた後、甲斐はそう答えた。公はゆっくりと歩き出し たが、立ったままでいたの望に気付き、いつもと変わらない口調で言った。 「はい、 ・・・じゃ帰ろ、清川さん」 「え? あ、あの・・・ 、ううん。私、先に行くところがあるから。 あ、ごめんね」 そう言って、公の止める声を振りきって、望は駆け出して行ってしまった。 その背中をしばし茫然として見送った後、公はため息をついた。 「ねえ、甲斐先生」 「ん? なんだ?」 「俺、清川さんに嫌われてるのかなあ?」 「はああ!?」 眼鏡の奥の目が点となり、ガクンとあごは落ち、甲斐は思いっ切り間の抜けた声を上 げてしまった。 「な、なんですか? その声は?」 真剣な表情で公がそう聞くと、甲斐は毒気の抜かれたような表情で力なく言った。 「主人ぉ」 「はい?」 「お前、長生きするよ」 「は?」 その言葉の意味が判らず、茫然とする公をしり目に、甲斐は笑いながらその場を後に していった。 『今のは、どういう意味なんだろう?』 公はそんな事を内心で思いながら、しばし北風の中で立ちつくしていた。 (うーーん。またかい!?)(苦笑) to be continue RZM-2「6」(第2集)